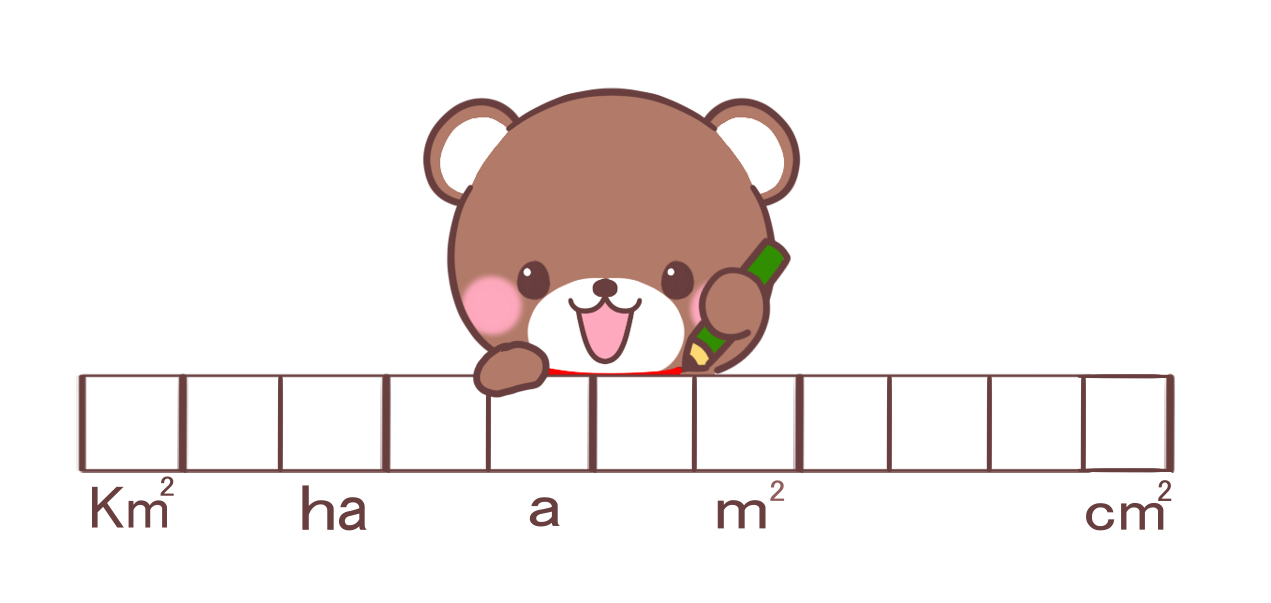- 2021年7月26日
今週の売買損益算は個数を考える問題です。
個数をかければいいだけですが、いろいろな応用問題に発展していきますので、一筋縄でいかない問題もあると思います。
原価・定価・割引を縦に書いて、単価・個数・合計金額を横に書いて、表にして整えることが、最も可視化できて考えやすい方法だと思います。
入試においては、この手の問題の80%くらいはつるかめ算になりますので、そのような心構えで問題を読んでいくと良いと思います。
第68話では原価を100円に決めて解くことが多かったですが、今回は、個数まで決めて解く問題もあります。
そのような大胆さを身につけましょう。
興味のある方はこちらにどうぞ
第69話:売買損益算③の概要
69・1
原価、定価、割引を順に求めて、個数をかけて、売り上げや総利益を求めていきます。
利益と売り上げのどちらで計算したらいいか判断しましょう。
69・2
原価が決まっていない問題です。
原価を100円にして、売り上げや総利益を求めて、実際とくらべましょう。
売買損益算で最も重要といっていい単元です。
69・3
売買損益算の定番中の定番のつるかめ算です。
利益の面積図にするか、売り上げの面積図にするかを見極めます。
原価割れすると面積図では対処しづらいので、売り上げにし、割引しても利益を出しているときは利益の面積図をかくと良いと思います。
売買損益算とつるかめ算は相性が良く、「定価で売れた個数が分からないければつるかめ算!」と反射的に決めつけてもいいくらいです。
69・4
原価や仕入れた個数が決まっていない場合は、適当に決めて解いて良いです。
例えば、仕入れた個数の20%が売れ残ったという問題ならば、1個の仕入れ値100円の商品を5個仕入れたということしていいです。
あくまでも比ではありますが、実数のイメージで解いていくことが大切です。
69・5
売れ残りが売れる問題です。
新たに仕入れて売れるのと、売れ残りが売れるのでは、売り上げの増え方は同じですが、利益は同じではありません。
その違いを理解することから始まります。
売れ残りが売れる場合は、売り上げの増えた分だけ、利益も増えます。
全部売れたら、利益は○円!という流れで考えましょう。
練習問題
| 番号 | 難 | 要 | 講評 |
| 1 | A | 総仕入れ値と、売上高を考えます。2割引は原価割れしているので、売上で考えた方がいいと思います。 | |
| 2 | B | ゼ | 3段階の売り方があります。それぞれの1個あたりの利益を求め、総利益を求めます。 |
| 3 | B | テ | 総利益から、割引価格での売上や単価を求めます。 |
| 4 | B | テ | 定価をすぐに求められるので、仕入れ値まで求めて、実際の金額で計算していくといいと思います。 |
| 5 | B | ゼ | 原価を100円にして、売上を求めてみましょう。 |
| 6 | B | ゼ | 原価を100円にして、利益を求めてみましょう。 |
| 7 | B | ゼ | つるかめ算です。すぐにつるかめ算と見抜けるようにしましょう。面積図は、縦を1個の売値にして、面積を売上にします。 |
| 8 | B | ゼ | つるかめ算です。面積図は、縦を1個の利益にして、面積を総利益にします。 |
| 9 | C | ゼ | 3段階の売り方がありますが、つるかめ算です。最後の割引で原価割れするので売上で考えます。定価で売れた分を除いて、割引で売った個数と、その売上を求めます。 |
| 10 | B | ゼ | 1割を捨てたので、大胆に10個仕入れたことにします。 |
| 11 | B | ゼ | 1個の原価100円で4個仕入れたことにします。少なくて違和感があるかもしれませんが、気にしないで解きます。 |
| 12 | B | ゼ | 1個の原価100円で3個仕入れたことにします。 |
| 13 | B | ゼ | あと10個売れたら、売上が6000円増え、利益も6000円増えると考えます。 |
| 14 | C | ヒ | 前半の文章から、仕入れた個数を求めます。それが分かったら、実際の売上を求めます。全部売れる問題でないときは、売上で解いた方が無難に解けると思います。 |
| 15 | D | ヒ | 予想と実際の利益の差が200円なので、売上の差も200円で、個数にすると8個差で、それが売れ残りの予想の個数の4割にあたります。そこから売れ残りの予想の個数を求めたら、「売れ残りが全部売れたら」というこのテーマのスタイルの解き方に入れます。 |
「難」は難度は以下の基準です。
A:確実に解けるようにしたい問題
B:サピックス偏差値50以上を目指す人向けの問題
C:サピックス偏差値60以上を目指す人向けの問題
D:特に難しい問題
※「要」は重要度で以下の基準です(B・C・Dのみ表記)。
ゼ:絶対に解けるようにしたい重要な問題
テ:よく出る典型題
ヒ:捻りのある問題
サ:地道な作業が必要な問題