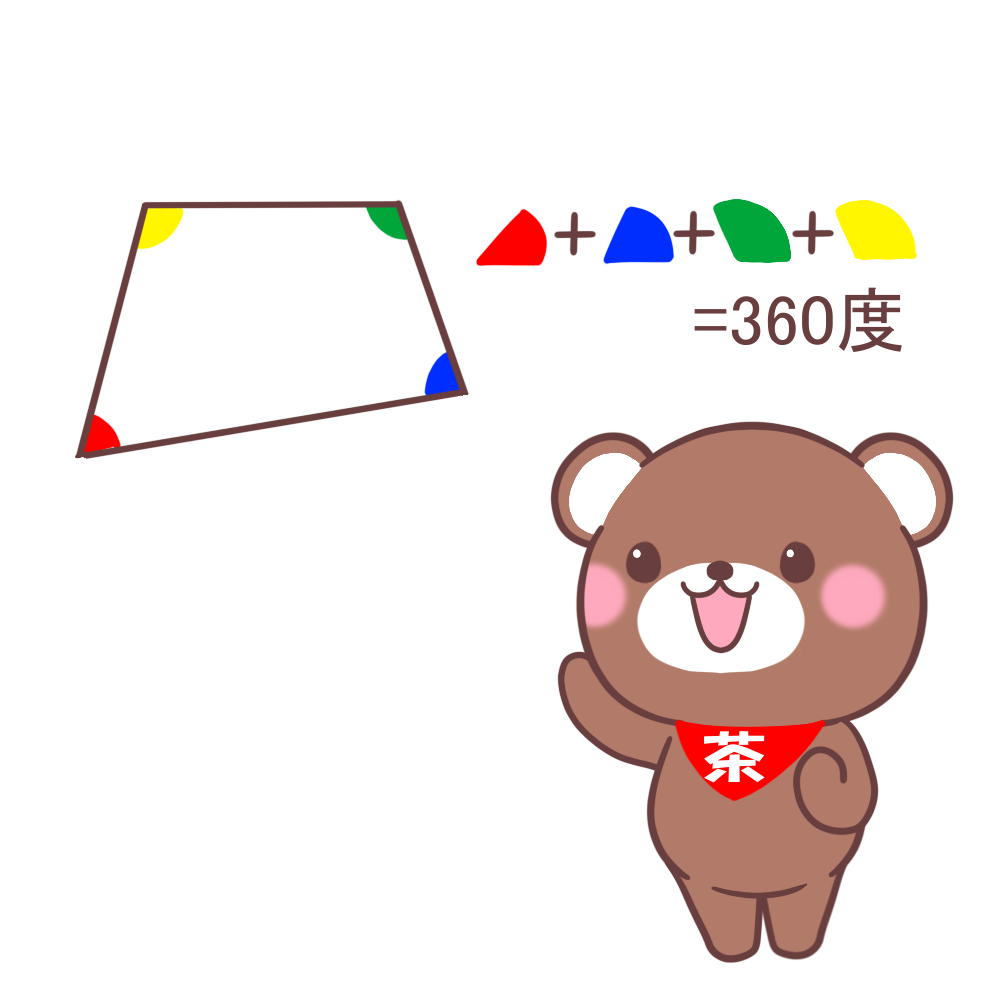- 2021年7月26日
この単元は一般的には線分図をかいて解きます。
対話式算数では、線分図の依存度はとても低いですが、和差算と、今回の「残りの○分の△」という表現のあるタイプの問題だけは、いままでは線分図を使うようにしていました。
これだけ線分図をかかない方針ならば、この単元の問題もかかないで解いてみたら?
ということで、試しに本編を大がかりに書き直してみましたら、目論見通り、線分図がない方が解きやすいです。
線分図がないとは、計算式だけとか暗算とか散らばって書いていいという意味ではなく、線分図以外のものを書いています。
表と呼ぶことにします。
算数が苦手な子は、端数のところを正しく線分図がかけないことが多く、また、「最後に全体の○分の△残る」という問題はレベルが高く、解けない子が多いです。
表にすれば、それが大幅に改善されると思います。
2021年版まで、この第57話のブログで、以下のように書いています。
- 線分図を大きくはっきりかく
- 線ごとに○、□、◇と記号を分ける
- 点線の位置を間違えないようにする
- 点線を下ろしたところから次の線分をかく
- めもりはかかない
- 分数は極力書かない
- 反対側もかく
- かき順にこだわる
これを見ると、やはり線分図は大変だと思います。
興味のある方はこちらにどうぞ
第58話:還元算
58・1
線分図と表の2つの解き方を示しています。
線分図はピストルの形に似ているので、ピストル型と呼んでいました。
58・2
端数のある問題です。
例えば本を読む場合、「残っていた分がAページで、今日Bページを読んだらCページ残った」としたら、それを「B+C=A」の式をつくれる力があれば、線分図よりも表の方が正解率は高まります。
58・3
ボールが跳ね上がる問題です。
単純な問題は、割合分数を何回もかけていく式を作って解きます。
複雑な問題は、図に、落とした高さと跳ね上がる高さの比を書き入れます。
58・4
最後に全体の何分のいくつが残るかが書いてある問題です。
「全体の」が2つあったら最小公倍数を使います。
記号を正しく使っていって、その後、記号を1種類に統一します。
これは線分図よりも表の方がはるかに簡単に解けます。
58・5
やや毛色の違う問題です。
最後から考えていくので、一般的に還元算に分類されるようです。
割合や比に慣れてくると、強引に最初から解いていく生徒さんがよくいますが、「最後が分かる場合は最後から」というように考えましょう。
1つだけはゆっくりていねいにやり、仕組みが分かったら、一気に表を埋めていきます。
ギアの切り替えが大事です。
練習問題
| 番号 | 難 | 要 | 講評 |
| 1 | A | 2種類の記号のまま解いても良いですが、解説では1種類の記号に統一するようにしています。 | |
| 2 | A | 1番の類題です。 | |
| 3 | B | テ | 3種類も記号が出てくるので、記号を統一する必要はないです。3種類の記号のまま、1つ1つ求めていきます。 |
| 4 | B | ゼ | 端数のある問題です。「取った分」+「残り」=「取る前に残っていた分」の式が理解できれば、線分図は不要です。 |
| 5 | B | ゼ | 4番の類題です。 |
| 6 | B | テ | 割合分数は1つ多くなりますが、4・5番と同様に解きます。 |
| 7 | A | ボールの跳ね上がる問題は、図をかかずに、割合分数をかける式だけで解いた方がすっきりして解きやすいと思います。 | |
| 8 | B | テ | 落とした高さの何分のいくつ跳ね上がるかを考えます。 |
| 9 | C | テ | 階段から落とす問題です。割合分数を比に直して、比を図に書き入れるようにします。 |
| 10 | B | ゼ | 全体を8と4の最小公倍数の8にします。端数がないので、難しくないと思います。 |
| 11 | B | ゼ | 全体を3と5の最小公倍数の15にします。一般的な線分図よりも表の方が解きやすいと思います。 |
| 12 | C | テ | 全体の金額を30にします。11番と似ていますが、端数の違いで解き方は異なります。線分図の場合は分配の法則で解き、表の場合は消去算で解きます。後者の方が簡単だと思います。 |
| 13 | B | ゼ | 最後の1800円から考えていきます。最後の操作前は、BがいくらでAがいくらかを丁寧に求めます。 |
| 14 | B | テ | 毎回、何分のいくつを渡すかが違いますが、1つ仕組みが分かったらスイスイ行けると思います。 |
| 15 | B | ゼ | これは割合ではありませんが、13・14番と同様に還元する問題です。割合ではないとは言え、最後の操作前は、特に丁寧に求めるところも同じです。 |
「難」は難度は以下の基準です。
A:確実に解けるようにしたい問題
B:サピックス偏差値50以上を目指す人向けの問題
C:サピックス偏差値60以上を目指す人向けの問題
D:特に難しい問題
※「要」は重要度で以下の基準です(B・C・Dのみ表記)。
ゼ:絶対に解けるようにしたい重要な問題
テ:よく出る典型題
ヒ:捻りのある問題
サ:地道な作業が必要な問題