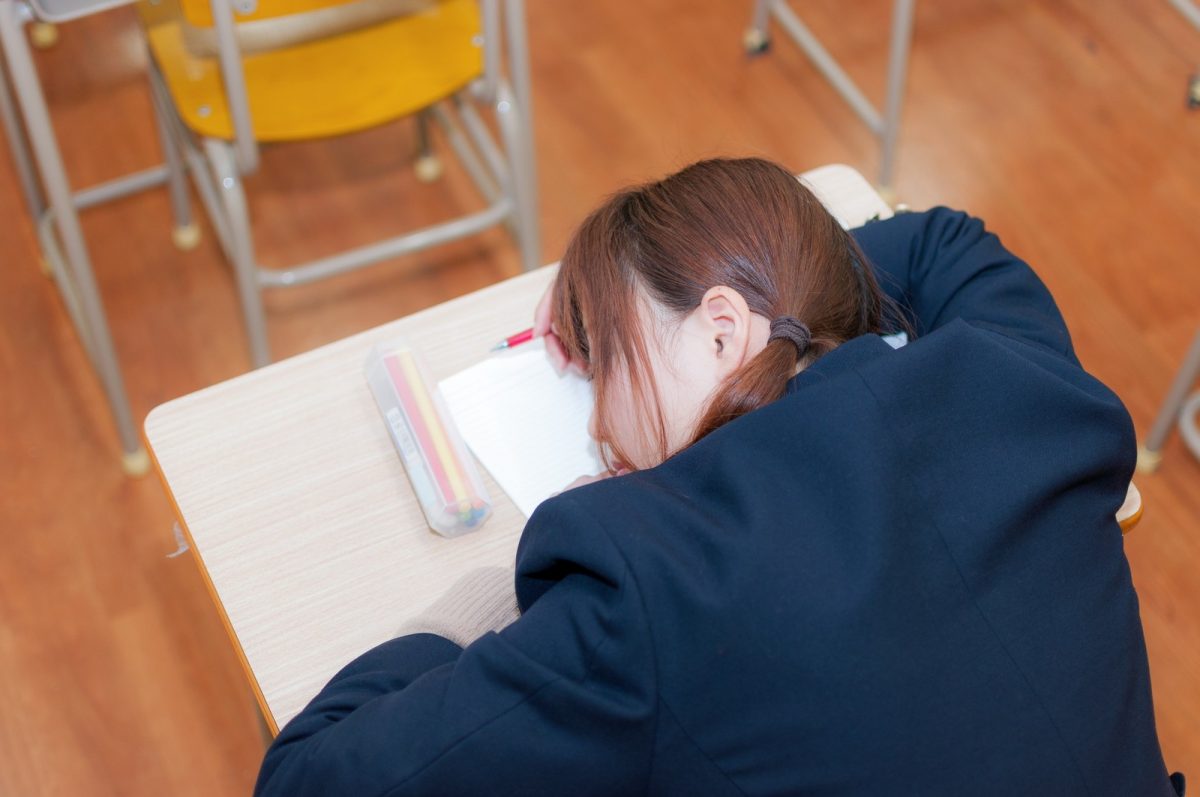テストが終わると、必ず、ミスがなければ○点とか、偏差値○とか、クラスが○になっていたとか、合格判定が○%になったというような声が聞こえます。
しかし、ほとんどの生徒さんにミスがあるので、その言葉は本当はおかしいはずです。
しかし、実際に担当して深く関わっていくと、つい、その言葉を使いたくなってしまいます。
不正解でも到達度が90%くらいになっていれば、不正解と片づけるのは正しい評価にはならないからです。
そうすると「80点取れるくらいの力がある」という表現はいいことになりますが、「偏差値55くらいの実力がある」とはやはり言ってはいけないと思います。
相対評価で、自分ひとりミスがなければという想定は正しくありません。
普通、表題の「ミスも実力のうち」という言葉は、前述の内容を指すと思います。
「ミスは誰でもしているんだから、それが実力だよ」ということは多くの人が言っているセリフでしょう。
しかし、今回は少し着眼点を変えてみます。
人間は、誰でもミスをします。
ミスのない人間はいません。
しかし、ミスの多い・少ないは人によって異なります。
今回のブログでは、さらに深く進めて、必然性のあるミスなのか、偶然のミスなのかに目を向けたいと思います。
例えば、以下の行動が起きているとします。
- 変な数字が出てきた、割り切れないけど立ち止まらない
- 筆算を狭いところに書く、遠くの枠外に書く、小さく書く
- 筆算が斜めにずれている
- 3・7・9・11・13で割れるか確かめない
- 求めた直後に検算をしない、量感を意識しない、常識と照らし合わせない
- 丸数字から数字をはみ出す
これを書いていくと、いったいいくつ書けるんだというくらいずらずら出てきました。
これらをやってしまっていることによるミスは、必然性のあるミスといえます。
上記のことをやっている限りは、何度も同じ間違いをします。
それに対して、何でこんな間違いをしたんだ!と、つい大人がカッとなってしまいそうなミスで、上記の事柄とは関係ないような偶然のミスというのは、実力がついてきたら解消されます。
月日がたち、入試に近づくにつれ、ミスが減る人が多いですが、それは、必然性のあるミスではなく、偶然のありえないミスがあったのが、実力がついたことによりミスが減ったと考えると、辻褄があいます。
逆に、ミスがいつまでも減らないという場合は、実力がついていないか、必然性のあるミスをしていることになります。
普通に勉強をしていて、全く実力がつかないということはないので、必然性のあるミスをしていると断言してもいいかもしれません。
つまり、4・5年生が模試を受けた後、間違い直しをやるときに、特に注意することは、必然性のあるミスをしているかしていないかということになります。
どっちかを判断することは簡単です。
何でこんなミスをしたんだをカッとなりがちなものが偶然のミスです。
カッとくるものはそのままスルーで、そうでないものに目を向けるという、心情と逆の処理をすると、正しい対処法になります。
例えば、スポーツで考えてみます。
野球の練習をとてもよくやっている選手と、サボりまくっている選手がいるとします。
とてもよくやっている選手が平凡なミスをしたり、四球を連発したりすると、監督はムッとくるかもしれません。
ところが、サボりまくっている選手が平凡なミスをしても、あいつは練習していないから当たり前と落ち着いて冷たい視線を浴びせると思います。
このように原因が分かっていることに対しては落ち着いてとらえることができるけど、原因が分からないとムッとくるのではないでしょうか。
算数のミスもそれと同じようになると思います。
しっかり直すのは必然性のあるミスの方です。
スカイプ指導をしているときも、「人間誰でもミスがあるから仕方ない」と慰めて言うときと、「わざと間違えている?と思いたくなる答案」と嫌味のようなことを言うときがあります。
少し言い方を変えます。
ミスをした子も、当然反省をしますし、今後気をつけようと思います。
しかし、上記のような直せるような悪い癖は、直さない限り、気をつけてもミスがでます。
原因不明のミスは、集中力を増したり、計算力を上げたり、経験値を上げることによって防げます。
つまり、大人が放っておいても、その子自身の自浄能力で解決できるというわけです。
まわりの大人が気をつけないと、模試の直しのときに、不要なことにこだわり、大切なことを放置しがちです。
同じミスでも対処法をはっきり分けることが重要だと思います。
今回のブログは以上になります。
いつもよりもお役に立ち度は増していると思っていますが、いかがでしょうか?
お役に立ちましたら、にほんブログ村のバナーボタンをクリック願います。
昨日の夜の段階で、1位とは14ポイント差で、2位でした。
語呂合わせというわけではありませんが、1月11日に1位を奪取したいと願っております。
ぜひ、皆様のお力を貸してください。