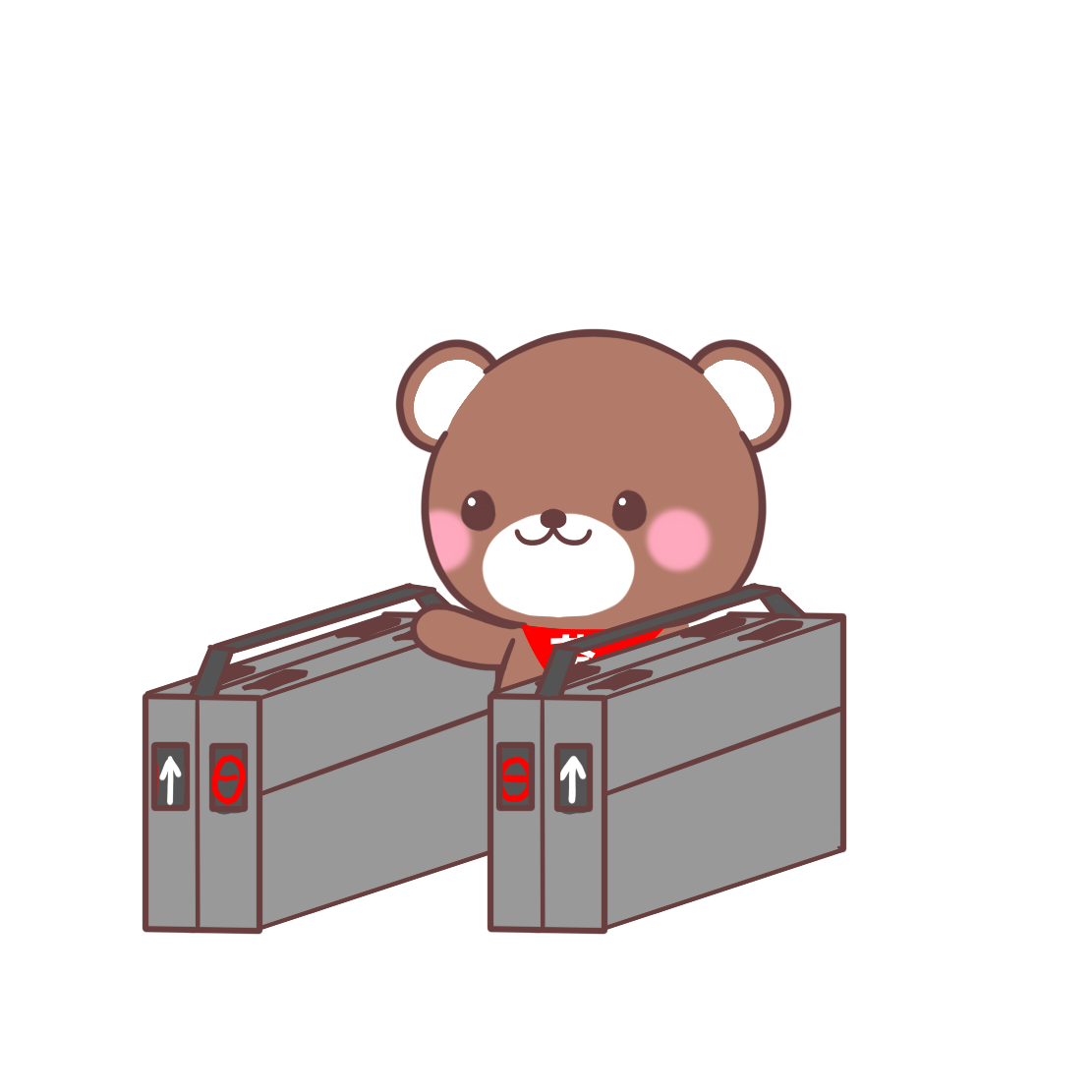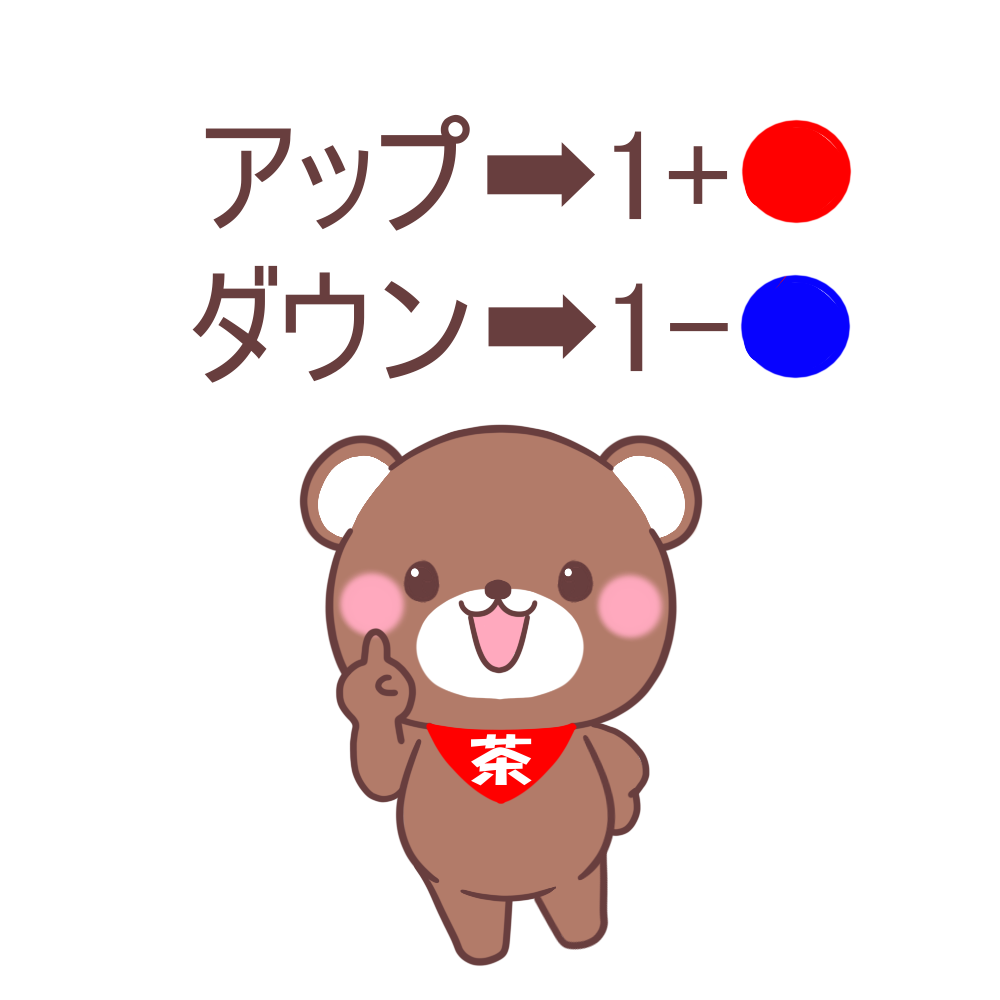- 2021年9月20日
今週は約数です。
4年生の1学期の間に分数やりたい
↓
通分に備えて公倍数を説明したい
↓
約分もあるし、ついでに約数をやろう
という流れです。
2021年版は、テーマを少々変更しました。
「旧7・3長方形の面積から辺の長さを決めよう」 → 「新7・3いくつだったら割れるか」
2021年版は順次、どのテーマも練習問題を3問にしていますが、「旧7・3」は3問になりそうもないということで、練習問題を第2話に移し、本編は削除しました。
「旧7・4」と「旧7・5」の2テーマを「新7・3」「新7・4」「新7・5」に膨らました形です。
順番を少々変えた関係で、会話をかなり変えました。
改良されたと思います。
興味のある方はこちらにどうぞ
第7話:約数の概要
7・1
約数の書き出し方を丁寧に説明しました。
塾の授業と同等以上に分かりやすく伝えています。
暗記の算数にならないような流れになっています。
書物ということもあり、身につきやすいと思います。
7・2
公約数は、
書き出して探す
↓
公約数は最大公約数の約数になっている
↓
最大公約数は連除法で求められる
という流れです。
ベン図を入れたり、図も豊富に使い、文字色も工夫しています。
分かりやすくなりましたが、とても分量のある章になりました。
互いに素まで説明していますし、例題も入れています。
普通の参考書は連除法の使い方を説明して終わりというものが多いですが、タイサンはどうしてそうするかに拘っています。
連除法は、算数ではすだれ算とも呼ばれます。
下に広げていくところが似ているからです。
お茶が好きな茶くま君は、夏はすだれの前で涼みながら熱いお茶を飲むのが好きらしいので、それを今回の画像にしました。
7・3
2つや3つの数を割って、それぞれあまりが出る問題です。
いくつだったら割れるかに注目します。
このテーマはあっさりですが、7・5で再び類題が登場するので、その2テーマを学習することで深く身につきやすくなると思います。
7・4
平等に分ける問題です。
最も基本的な約数の文章題です。
ここまでの内容がしっかり身についていたら、サクサク進むことでしょう。
来週、倍数を学習すると、この手の問題がいろいろ混同して混乱しやすくなります。
「約数」というところと、「公約数」というところと、「最大公約数」というところを気をつかって間違えないように使い分けることも大切です。
それが数の性質を得意にする一歩かもしれません。
7・5
「7・3」と「7・4」を合わせたような問題です。
平等に分けて、端数のある問題です。
機械的に覚えないで、どうなれば分けられるかをイメージしましょう。
リンゴの図を使って分かりやすく書いています。
練習問題
| 番号 | 難 | 要 | 講評 |
|---|---|---|---|
| 1 | A | 約数をしっかり書き出しましょう。 | |
| 2 | A | 約数をしっかり書き出しましょう。ここで平方数の約数は奇数個ということを体感しても良いと思います。 | |
| 3 | A | 小さい方から3番目を考えます。 | |
| 4 | A | 連除法を利用しましょう。 | |
| 5 | A | 連除法を利用しましょう。 | |
| 6 | A | 数が3つになっても連除法を使います。 | |
| 7 | B | ゼ | 端数を処理してから約数を書き出しましょう。 |
| 8 | B | ゼ | 端数を処理してから公約数を求めましょう。 |
| 9 | B | ゼ | 手順通り、端数を処理して、最大公約数を求めて、その約数を書き出して公約数を求めます。その中で、最大と最小を求めましょう。 |
| 10 | A | 108本を分けるので、人数は108を割れる数になります。 | |
| 11 | A | 「リンゴを分けたい」→「ミカンを分けたい」→「両方分けたいから公約数」と考えます。 | |
| 12 | A | 公約数を求めたら1袋の個数をそれぞれ求めていきます。 | |
| 13 | B | テ | 分けられるにはジュースが何本必要かイメージして考えましょう。機械的に解けても意味がありません。 |
| 14 | B | ヒ | まず、Aグループの人数の候補を2つ求めます。その2パターンをBの条件に当てはまるかを考えます。 |
| 15 | B | ゼ | ミカンだけ不足なので、何個だったら分けられるか考えましょう。 |
※「難」は難度は以下の基準です。
A:確実に解けるようにしたい問題
B:サピックス偏差値50以上を目指す人向けの問題
C:サピックス偏差値60以上を目指す人向けの問題
D:特に難しい問題
※「要」は重要度で以下の基準です(B・C・Dのみ表記)。
ゼ:絶対に解けるようにしたい重要な問題
テ:よく出る典型題
ヒ:捻りのある問題
サ:地道な作業が必要な問題