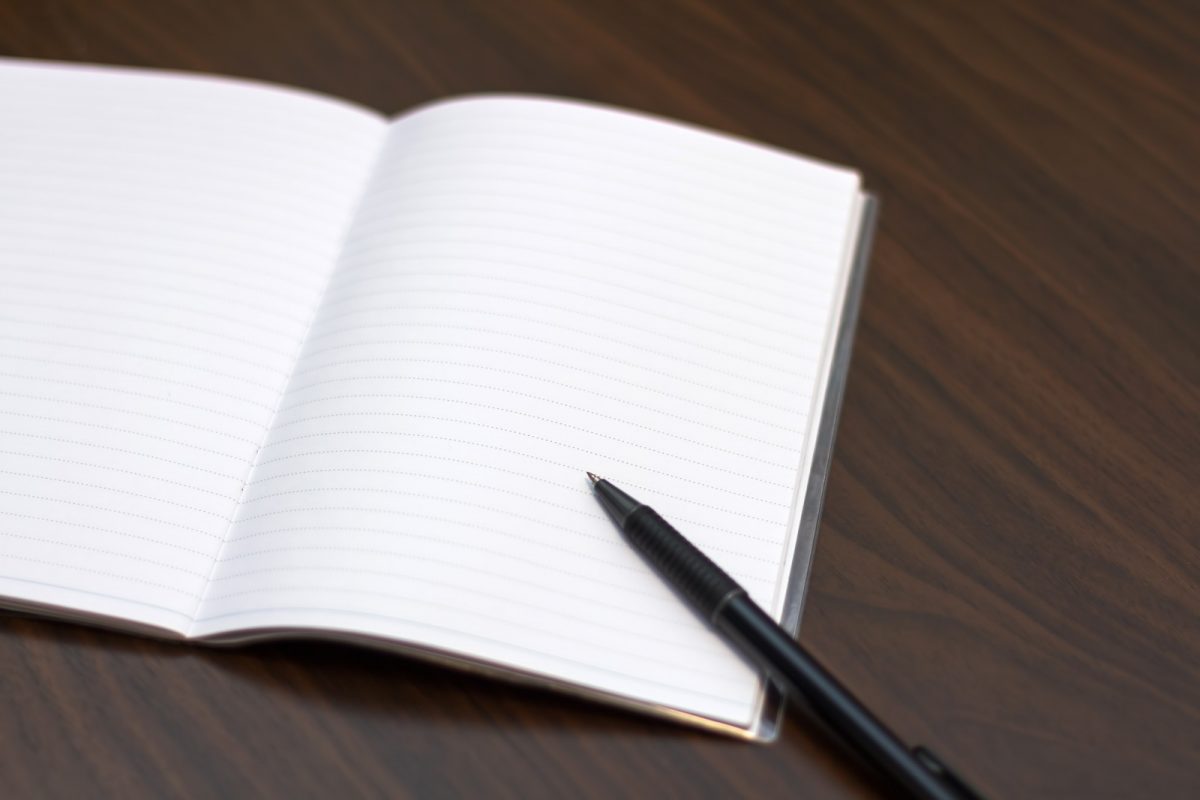- 2017年6月2日
マラソンでよく見る光景ですが、10㎞地点くらいで、スパートして大きく前に出る選手がいます。
先頭集団がそれについて行かない場合、ほぼ100%といっていいくらい、大きく前に出た選手はやがて集団に飲み込まれ、その後、先頭集団にもついて行けずに後退するという姿です。
受験勉強の先取り学習も、このようなイメージを重ね合わせますと、二の足を踏みます。
塾講師をしていますと、入塾段階で「公文で○まで進みました」「既に○○は学習しました」と聞くことが多いです。
どんなものだろう期待してみますと、実は、大したことが無いというケースが多いです。
大したことが無いというのは、学力が高いかどうかです。
学力が高くなければ、すぐに追いつかれます。
例えば、つるかめ算の面積図を既に知っていたとします。
しかし、塾の授業でつるかめ算の面積図を教えたら、みんな身につきます。
といいますか、上位のクラスならば、家で徹底的に演習して身につけてきます。
翌週に確認テストをしますと、先取り学習の優位性がありません。
この流れですと、先取り学習は意味が無いと感じられると思います。
先取り学習で既に知っている内容と油断していたら、むしろ、大事なポイントを聞き逃し、逆転されてビハインドの立場となってしまう恐れもあります。
答えが出る計算式だけ身につけて、それでその単元終了という先取り学習をしていたら、このような状況になると思います。
先取り学習を生かすためには、まわりの子たちに追いつかれないという姿勢が必要です。
追いつかれないためには、難しい問題まで手をつけることです。
先取り学習には、当教材の対話式算数をお勧めしていますが、練習問題は、難易度を示すA~Dの記号をふっています。
Dはほとんど無いので、実質3段階と捉えていただきたいのですが、先取り学習の段階ではBまでで良いとします。
そして、塾で学習したときに、Cまできちんと解けるようにするという感覚です。
先取り学習をしていなかったらCまでできなかったはずなのに、先取り学習をしているからCまでできたという状況になれば、それは先取り学習をしているから難しい問題まで手をつけられたことになります。
このように、毎回Bまでの子、あるいは無理矢理Cを取り組んで、答えを見て、強引に解法を身につけたことにしている子と比べ、悠々とCまで取り組めば、その差は縮まることはないのではないでしょうか。
先取り学習無しで、毎回Cまできちんと身につける優秀な生徒さんとはしのぎを削った競争になるかもしれませんが、その競争ができるのは、先取り学習の成果と言えます。
そのためには、先取り学習の段階で、相当しっかり身につけないといけません。
やらないよりはやった方が良いという感覚で、質の低い先取り学習をしていましたら、メリットはなく、逆にマイナスになる恐れもあるという状況になります。
先取り学習をやって、その優位性を維持するためには、下の学習スタイルがモデルケースです。
- 授業で新しい知識の吸収、発見ができるように、メリハリをつけて授業を聞く
- 家で、授業で何が身についたか確認する
- 授業の復習は、易しい問題は間引いて、その教材の最高峰レベルや他の教材の応用問題を取り組む
この上記3点が毎週継続してできれば、先取り学習の効果が持続し、やがては「この子は優秀だから、先取り学習ができたんだね」となります。
先取り学習をしなければ普通の子で、やったから優秀になったという感覚にはならないと思いますが、それはどうでも良いことだと思います。
結果が良ければすべてです。
先取り学習と予習は大きく異なるものですが、学習の仕方は同じだと考えて良いと思います。
予習の仕方を相談しますと、「とりあえず読んで、理由は授業で教われば良い」と言われます。
それで本当に効果があるの?と思われがちな回答だと思います。
それにつきましては、また、次回のブログで書こうと思います。