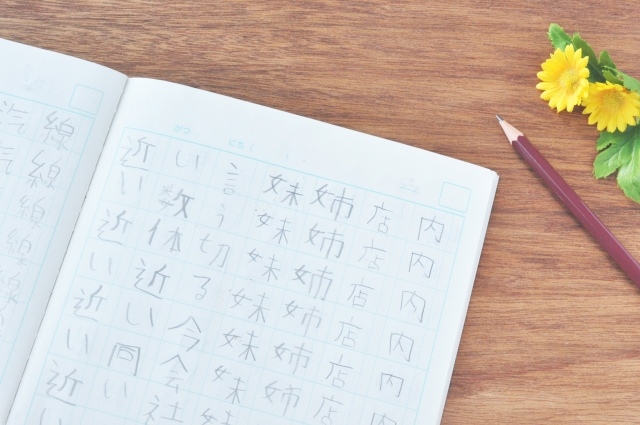- 1. 筋道を立てる力を育てる、唯一のトレーニング
筋道を立てる力を育てる、唯一のトレーニング
受験算数の多くの単元では、「この条件から、何を求められるか?」を考える力が求められます。
割合の文章題も、速さの文章題も、平面図形も、立体図形も――
いずれも「与えられた条件をどう使うか」という思考が中心です。
もちろん、この力は必要です。
ただし、この思考は受験生の差はつきにくいです。
■ 多くの単元では、差がつきにくい理由
なぜ差がつかないのか?
それは「条件の使い方」は、経験がものをいう分野だからです。
「経験で差がつく」部分は、実は多くの受験生で大差がありません。
ある問題を解くために必要な経験は、上位層の子ならほとんど全員が持っています。
だから、
「知っていたからみんなと同じように解けた」
「知らなかったからみんなと同じように解けなかった」
というケースが非常に多い。
つまり、経験で上回るのは難しい世界なのです。
具体例を見てみましょう
① グラフを点対称に見て速さを整理する
→ ほとんどの受験生が経験済み。経験があれば誰でもできます。
② 食塩水の問題で「濃度」ではなく「食塩:水」の比で考える
→ 慣れていれば鮮やかにできますが、正答率に大差は出ません。
③ 都合の良い“影武者”を作って整理する
→ 経験していても、それを自発的に使えるかどうかが差になります。
④ 電車の問題で、先頭と最後尾を別々にダイヤグラムに描く
→ 経験がなければまず使えません。経験があっても、実戦で活かせる子は少ないです。
このように、「経験しているかどうか」よりも、本質的な差は、“経験をどう活かせるか”という力にあります。
条件の使い方を磨く勉強は、ある程度やれば誰でも身につきます。
しかし、経験で終わってしまってはアドバンテージは作れません。
「活用する力」まで到達すれば差が生まれそうですが、上位層の多くはすでにその段階に達しています。
しかも、活用がとても難しい問題ほど、誰も上手く活用できないため、“活用の力”で差をつけるのも実際には難しいのです。
■ そこで差がつくのが「場合の数」
それに対して、数の性質・場合の数・論理・一部の規則性の単元は別格です。
これらの分野では、「条件の使い方」ではなく、筋道を立てて考える力が問われます。
「どんな流れで答までたどり着けるか」といった“思考の構築力”が必要になります。
この「筋道を立てる力」こそ、人によって大きく差がつく領域なのです。
■ 筋道を立てる力は、他の単元にも波及する
筋道を立てる力を鍛えると、その影響は算数全体に広がります。
割合でも、速さでも、図形でも、筋道を立てる力が問われる問題があるからです。
ところが、他の単元ではその筋道を立てる練習がしにくいです。
- 数の性質や論理は高度すぎて、初学者には難しい
- 割合や速さは、条件処理が中心で、問題を厳選しないと筋道練習にはならない
- 図形は、他分野への波及が少ない
だからこそ、“場合の数で筋道を立てる訓練をする”のが最も効率的で実践的なのです。
■ 具体例:筋道を立てれば、難問も「簡単になる」
たとえば次のような問題があります。
111222333445 から 3つの数字を選んで、3桁の整数を作るとき、
何通りの整数ができますか?
初めて見ると「同じ数字がたくさんあって複雑そう…」と感じますね。
でも、筋道を立てれば一気に見通しが立ちます。
思考の流れ
① 同じ数字が多くてやりづらい。
② 「4と5が3個ない」から困っている。
③ ならば、4と5を“追加して考える”。
④ そのあと、余計に数えてしまった分を引けばいい。
計算してみましょう
111222333444555 と考えれば、
それぞれ5個ずつあるので 5×5×5=125通り。
そこから、できないパターンを引きます。
「444」「555」「55□」「5□5」「□55」など14通りが作れません。
したがって、
125-14=111通り。
一見複雑な問題が、筋道を立てることで解答までの道が整理できたのです。
これが、「場合の数を学ぶ価値」です。
条件を上手く使ってという問題ではなかったことはおわかりになると思います。
■ もう一つの考え方:「型」で分類して整理する
同じ問題でも、もう一つのアプローチがあります。
それが「型で考える」方法です。
この場合は、数字の並び方をAAA型・AAB型・ABC型に分類します。
- AAA型(すべて同じ数字) … 111、222、333 の3通り
- AAB型(2つが同じ数字) … 4×4×3=48通り
- ABC型(すべて異なる数字) … 5×4×3=60通り
3+48+60=111通り。
結果は同じでも、筋道はまったく異なります。
■ どの道筋を選べるかで「考える力」の質が変わる
このように、同じ答えにたどり着くにも、筋道はいくつもあるのです。
- 「一度全体を作って、余計な分を引く」包括的発想
- 「型に分類して、抜けや重なりをなくす」構造的発想
どちらが“良い”というわけではありません。
大切なのは、複数の道筋を思いつけるかどうか。
そして、それぞれの特徴を理解したうえで最適な方法を選べるかどうか。
これが、場合の数が鍛える“筋道を立てる力”の本質です。
■ 筋道を立てる練習には、「場合の数」一択
「筋道を立てる力」は、数の性質・一部の規則性・論理問題でも鍛えられます。
しかし――
これらの単元はどれも内容が高度で、4年生・5年生のトレーニングとしては不向きです。
数の性質は中盤以降になると難易度が急上昇し、論理問題は文章の抽象度が高くなります。
規則性も、難度が上がると、数の性質が絡み、複雑になりやすい。
その点、場合の数は様々な難度の問題があり、難度の調整がしやすく、ちょっと難しいけれど、やればできるレベルの問題が豊富にあり、筋道を立てる練習に最も適しています。
だから私は、
4・5年生の”筋道を立てる思考力トレーニング”としては、場合の数一択だと考えています。
他の単元では得られない「筋道を立てて俯瞰する習慣」と「論理の型」が、ここで身につくのです。
■ 大手塾が場合の数を軽視する理由
大手塾では、場合の数はそれほど重視されません。
理由は単純です。
「効果が出にくい」と思われているからです。
ただし、これは“誤解”です。
塾の授業は「テストで点を取る」ことを目的にしているため、時間をかけて考えさせるよりも、
公式や手順を“覚えさせて”解かせます。
するとどうなるか?
筋道を立てる力が育ちません。
最初から教えられてしまえば、“考える時間”がゼロになります。
これでは筋道を立てる力は鍛えられません。
だから、塾では「場合の数をやってもさほど効果は無い」と結論づけてしまうのです。
実際には、「ヒントで誘導されながら、考えることで筋道を立てる力がつく」のが場合の数。
つまり、“取り組み方”の問題なのです。
■ 「場合の数だけ苦手な子」と「場合の数だけ得意な子」
- 場合の数だけ苦手な子:筋道を立てるのが苦手
- 場合の数だけ得意な子:条件処理は苦手でも、筋道を立てるのが得意
条件処理は経験とともに上達しますが、筋道を立てる力はそう簡単には身につきません。
だから、「場合の数だけ得意」な子のほうが、将来の伸びしろが大きいのです。
■ 難問に必要な“緻密さ”も、場合の数で鍛えられる
難問を解く力というのは、瞬発力ではありません。
必要なのは――
ゆっくり丁寧に、緻密に、そして工夫して進める力。
難問で差が付くのは、派手なひらめきではなく、地味な整理力と正確な手順が勝負を分けます。
ところが、この“緻密さ”は、難問の演習では身につきません。
なぜなら、難問は「考え方の練習」は、その問題に特化しすぎて、汎用性がないからです。
一方で、場合の数はどうでしょう。
やや易しい問題を、ゆっくり・慎重に・丁寧に進める練習ができます。
しかも、その過程すべてが「整理する力や正確な手順」になります。
つまり、場合の数は“緻密に考える力”を鍛える練習場なのです。
■ 結論:場合の数をやる子は、考える子になる
場合の数を学ぶと、「答えまでの道筋を考える習慣」ができます。
- 複雑な問題も筋道を立てれば整理できる
- 自分の手で道筋を見つける快感がある
- 他の単元でも応用できる
そして、「構造で考える」ようになります。
これが、受験算数における最大の差別化です。
「場合の数を制する者が、難関中を制す」
それは決して誇張ではありません。
なぜなら、「場合の数」は、考える力を磨く唯一の実践型トレーニングだからです。