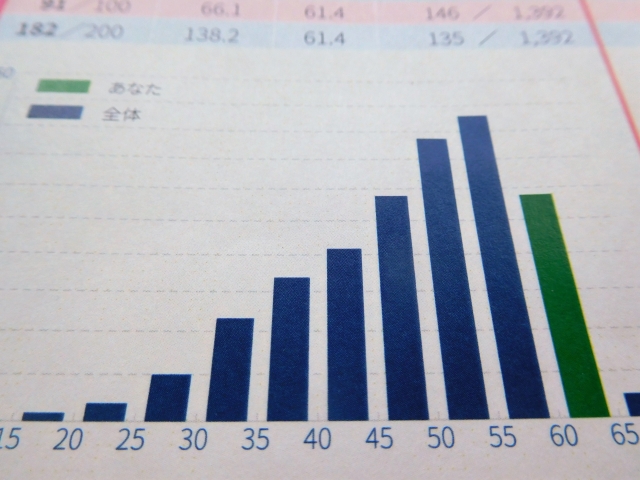親が子に算数を教えるときに本当に大切なこと
中学受験の算数は、家庭でも親が子に教える場面が少なくありません。
目的はさまざまです。
「テストの点数を上げたい」
「宿題を終わらせたい」
「分からない問題を理解させたい」
どれも正しい目的ですが、私が最も大切だと思うのは、子どもが考える時間をしっかり確保することです。
「考える時間」こそが学びの本質
解けない問題というのは、子どもがまだ十分に考えていないからこそ解けないのです。
そして「普通に教わった」程度では解けるようにならなかった問題だからこそ、目の前に残っています。
ということは――
解けるようにするためには、「普通以上の教え方」が必要になります。
でもそれを親が完璧にやるのは、実はとても難しいことです。
だからこそ、教え込むのではなく、考える時間を与えることが一番大事なのです。
効果的なサポートの仕方
「じゃあ、放っておけばいいの?」と思う方もいるでしょう。
もちろんそうではありません。
子どもが迷子にならないよう、具体的なヒントを出すのです。
- 「ここをよく読んでごらん」
- 「これを書き出してみよう」
- 「この数字をまず求めてみたら?」
こうした声かけは、余計な情報を与えすぎず、子どもが自分で考えるきっかけになります。
塾の教材を見て「この一言がヒントかな?」と探すつもりで関わると、的確なアドバイスができるようになります。
時間がかかるのは無駄ではない
「一問にこんなに時間をかけて効率が悪いのでは?」と不安に思う親御さんもいます。
ですが、じっくり考えて、自分の頭で理解した経験は、効率を超える深い学びになります。
元大リーガーのイチロー選手がかつて言っていました。
「無駄がなければ深みが出ない」
算数の学習もまさに同じです。
効率よく答えを得ることばかり考えると、深みのある学習にはなりません。
答えを教えてしまうリスク
算数が得意なお父さんお母さんほど、つい「答え」を言いたくなってしまうものです。
でも、それを繰り返すと高い確率で子どもの算数は伸びません。
なぜなら、考えずに理解できないまま“解決”してしまうからです。
考え抜く経験を奪ってしまうのです。
「原則を守る」ことの徹底
子どもの学習で大切なのは、正解を出すこと以上に、正しい作法を守ることです。
- 「この単元は必ず図を描く」と決めたら、正解できてもできなくても図を描く。
- 「表を書いて整理する」と決めたら、面倒でも必ず表を書く。
楽な方向に流れると、その場は解けても学習効果は下がってしまいます。
原則を守って取り組むことで、学習姿勢そのものが強くなります。
まとめ
親が子に算数を教えるとき、最も大切なのは 「考える時間を奪わない」こと。
- ヒントは出すけれど、答えは言わない
- 効率よりも深みを大切にする
- 原則を守り、正しい作法を徹底する
こうした関わり方ができれば、子どもは「考える力」を育て、やがて自分で算数を切り拓けるようになります。
受験算数において、これは何よりの財産です。