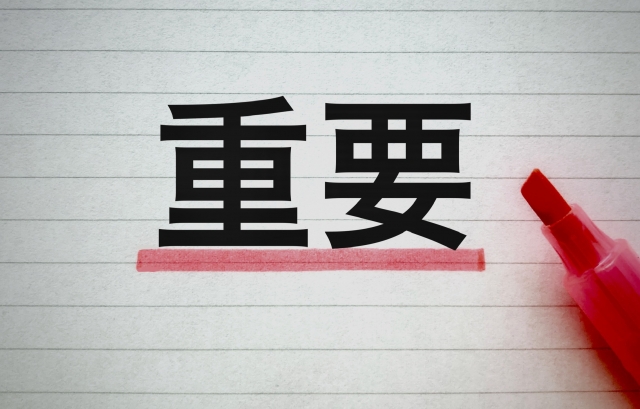5年生から受験勉強を始める人の理想的な4年生の過ごし方
「中学受験は4年生から始めないと遅いですか?」
保護者の方からよくいただくご相談です。
結論から言うと、5年生からのスタートでも十分に間に合います。
しかも私は、難関中学を目指す場合でも「5年生から始めた方が理に適っている」と考えています。
なぜ5年生スタートが理に適っているのか?
4年生から高度な受験勉強を始めると、多くの場合「覚える算数」になってしまいます。
つまり「こういうときはこう解く」というパターン暗記に偏ってしまい、思考力や柔軟な発想を育てる余地がなくなってしまうのです。
その弊害は大きく、後から修正するのは容易ではありません。
ですから、あえて4年生の段階では“やらない方がいい勉強”を避けることが、とても大切なのです。
では、4年生では何をやればいいのか?
「受験勉強をしなくていい」ということではありません。
むしろ、この時期だからこそ効果的に伸びる単元があります。
特におすすめなのは次の3つです。
1. 角度
角度は、受験算数の中でも数少ない“良質な単元”です。
- 作戦を立てて解く
ただ作業的に計算するのではなく、「どのように攻めるか」を考える力が問われます。まさに算数の醍醐味を体験できる分野です。 - 別解が豊富
同じ問題でも複数の解法が存在し、「あ、こんな考え方をすれば一気に解けたんだ!」という感動体験を味わえます。これが子どもの算数を好きにさせる大きなきっかけになります。 - 思考力勝負
角度の問題は計算量が少なく、“思考そのもの”で勝負する分野です。計算が得意でなくても、発想力で十分に戦えます。 - 算数の基本作法が身につく
角度の問題では、「当たり前のことをくどくど書かない」「考える前に闇雲に補助線を引かない」など、算数の基本姿勢を自然に学ぶことができます。これは後の算数全般に通じる大切な作法です。
このように、角度の学習は「楽しさ」「発想力」「作法」の3つを兼ね備えた、まさに中学受験算数の入り口として理想的な単元です。
4年生のうちにじっくり取り組めば、5年生以降の武器になることは間違いありません。
2. 場合の数
ただ公式を覚えるのではなく、書き出しから始めて、作業を通じて理解することが重要です。
「計算にどう移行するか」を自然に身につけることが理想の学習法です。
単純に解き方を暗記して演習を重ねる学習では、デメリットが多いので要注意です。
3. 計算(暗算・図形の面積)
暗算力や、面積の感覚は“基礎体力”にあたります。
難しい知識を詰め込むよりも、計算処理を速く正確にできる力を磨いておくと、後々大きな差になります。
具体的な教材活用法
「何をやるか」以上に「どの教材でやるか」が重要です。
例えば「場合の数」とタイトルが付いているからといって、どの教材でも良いわけではありません。
私のお勧めは、まず 『中学入試算数リスタート』の「場合の数」 を先行して学習すること。
ある程度知識を身につけたら、続いて 『小4長期場合の数』 に取り組むスタイルです。
トータルで20時間ほどで一通りの学習が可能です。
さらに余裕があれば、次のステップとして 『小5長期場合の数』 に挑戦するとよいでしょう。
知的遊びも効果的
4年生のうちは、算数パズルなどの知的な遊びも大きな意味を持ちます。
ただしこれは「受験勉強」というよりは「知的な遊び」の扱いです。
ナンプレ、カックロ、将棋や囲碁といったものは、戦略的思考を鍛える良いトレーニングになります。
学習の質を下げないことが最優先
大事なのは、「まだ時期尚早なものは避ける」という姿勢です。
「とりあえず受験っぽい問題を与える」のではなく、「今この時期に伸びること」「覚える算数に陥らないこと」に絞って取り組む。
これが、5年生から本格的に受験勉強を始める子にとって、理想的な4年生の過ごし方です。
まとめ
- 4年生から高度な受験勉強を始めると「覚える算数」になりやすい
- 5年生スタートの方が、理解を伴った学びになり理に適っている
- 4年生では「角度」「場合の数」「計算(暗算・面積)」をとことん伸ばす
- 適切な教材選びが最重要
- 知的な遊びも大切にする
- 学習の質を下げないことを最優先に
親が日常生活でできるサポート(声かけ・環境作り)
4年生の1年間は「準備期間」です。
この時期に、親がちょっとした工夫をすることで、5年生スタートがスムーズに進みます。
1. 「勉強=楽しさ」と結びつける声かけ
「また勉強しなさい!」ではなく、
「今日はどんなこと分かった?」
「これ面白い問題だね!」
と、学習を“話題”にしてあげると、子どもは自然と勉強をポジティブに捉えます。
2. 数字が自然に出てくる生活環境
- 買い物で「3つで600円だから、1ついくら?」
- お料理で「このケーキを6人で分けたら何度で切ればいい?」
- 外出で「駅まで15分、歩く速さを考えると何時に出たらいいかな?」
日常の中で数字をさりげなく飛び交わせると、「数字感覚」が自然に育ちます。
3. 集中できる環境づくり
机の上はシンプルに。余計なものを置かない。
学習時間を「短く・集中して・毎日同じ時間帯に」設定することで、習慣化が進みます。
親は「時間を区切る役目」と「邪魔しない役目」に徹するのがポイントです。
4. 努力を認める習慣
結果だけを評価するのではなく、
「今日はここまで頑張ったね」
「昨日より集中してたね」
と、過程や努力を認める声かけをしましょう。
結果主義に偏らないことで、子どもは安心して挑戦できます。
まとめ
4年生の時期は、ただ「勉強させる」よりも、
- 学習を楽しめる声かけ
- 数字に触れる日常の工夫
- 集中できる環境づくり
- 努力を認める習慣
この4つが、親ができる最高のサポートです。
こうした下地を整えておけば、5年生からの受験勉強はスムーズにスタートし、無理なく大きな伸びにつながります。