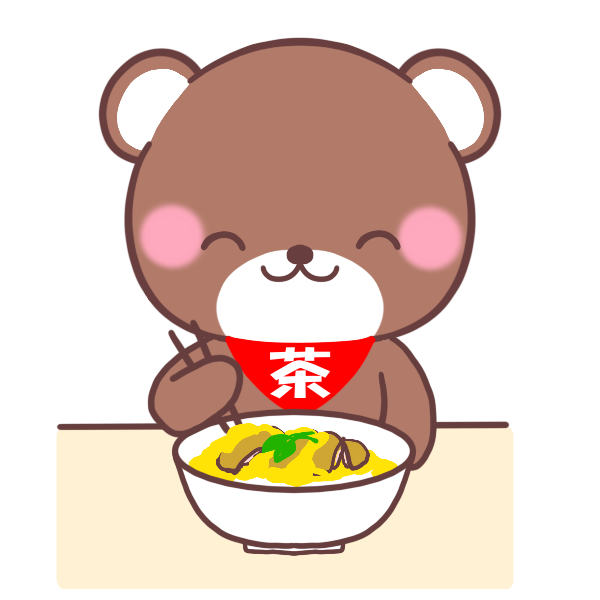- 2021年6月7日
私は、サピックスで専任講師をスタートしたので、過不足算は、サピックス伝統の面積図でした。
しかし、あまりしっくりこなかったので、書き出していくスタイルに切り替えました。
その後、川崎の塾で働き、上司が「俺が小学生のときは過不足算は苦手だったけど、この仕事をして、線分図に触れて、初めてよく理解できた。過不足算は線分図しかあり得ない!」と言っていました。
当時は、自分の解説を塾のメイン解説にしたかったということもあり、機嫌を損ねるのはまずいと思い、私も線分図派に切り替わりました。
その後、書き出していくスタイルに戻ったり、比例のような書き方をしたり、厚みをもたせた線分図などいろいろ試しました。
いっそのこと、①を使って方程式のようにしてみようということで、前回の改訂では「割合と比」で扱うことにし、4年生から5年生に格上げしました。
ところが、スカイプ指導で、実際に説明してみると、割合と比では扱いにくいと実感することが多かったです。
このような試行錯誤をくり返し、現在の結論としては、「はじき」や「しみこし」や「単価個数合計金額」などのようなかけ算の形の表です。
過不足算を特殊な単元とするよりも、「過不足算もちょっと変形しているけど、同じ表でできるね!」とした方が良いと考えています。
今回、5年で扱うことはそのままにして、大幅に「本編」と「練習問題の解説」を書き換えました。
過不足算は、つるかめ算の面積図のように劇的に分かりやすい解き方がある訳ではありません。
それならば、解き方の統一を優先させた方が良いと思います。
このあたりは、算数講師それぞれで考え方が異なる部分だと思います。
興味のある方はこちらにどうぞ
第62話:過不足算
62・1
例題1と2は、かなり簡単な導入問題にしました。
書き出していく方法と、表の方法を書いています。
こういうやさしい問題で、表を書く習慣をつけた方が良いと思います。
その後、例題3~5で「過不足パターン」・「過過パターン」・「不足不足パターン」の3つを扱い、さらに「分ける」ではなく「集める」問題を入れ、合わせて例題6問というボリューム満点のテーマとなりました。
線分図もかきましたが、表で説明することをメインとしています。
あまりと不足の差は、たすことになりますが、どうしてたすのかをイメージできることが大切です。
62・2
入試レベルの問題です。
基本型になっていないので、基本型に直してから解きます。
分かりにくい問題は人数を書いていって、イメージを湧かしてから基本型にします。
62・3
62・2の応用的な問題です。
書いていって、あまりや不足を把握して、そこから過不足算スタイルで解くという流れをつくりましょう。
62・4
箱から2種類の玉を取り出す問題です。
過不足算と同じ原理ですが、差集め算と呼びたくなるテーマです。
過不足算と同じような解き方で求められます。
表を書くことを勧めています。
62・5
個数を逆にする問題です。
入試ではよく出るテーマです。
金額の差から、個数の差を求めます。
覚える算数でも解けますが、どうして個数の差になるのか、自分なりの言葉で説明できることが望ましいです。
面積図の解き方も解説していますが、面積図で解ける問題と解けない問題があります。
どういう問題で面積図を使えるかを判断する力が必要です。
練習問題
| 番号 | 難 | 要 | 講評 |
| 1 | A | 過不足算の基本型です。解き方のスタイルを身につけましょう。差を考え、人数を求めます。 | |
| 2 | A | これも差を考え、人数を求めます。 | |
| 3 | B | テ | くばる問題ではなく集める問題なので、正しく考えていきます。過不足算は言葉が逆の意味になりやすく紛らわしいので、答えを2通りの方法で求める習慣をつけると良いと思います。 |
| 4 | B | ゼ | いすの差ではなく、すわれる人数の差を求めます。 |
| 5 | B | ゼ | 4人分あまるということは、12本あまると考えます。 |
| 6 | B | ゼ | 1教室で44人のとき、あと何人入れるかを慎重に求めましょう。 |
| 7 | C | テ | 4人に5個ずつ、3人に4個ずつ、残りの子供に3個ずつというのを、全員3個ずつにしたらどうなるか?と考えます。人数が分からない人たちの個数にそろえます。 |
| 8 | C | テ | 7番の類題です。人数が分からない人たちに個数をそろえます。 |
| 9 | C | ヒ | リンゴとミカンの2種類の果物があり、個数が違うので、過不足算の型にはなりませんが、ミカンを10個増やしてリンゴと同数にしたら、過不足算で解けるようになります。このように工夫して加工する力が、算数では必要です。 |
| 10 | A | 差集め算と呼びたくなる問題です。1日の差を考えます。 | |
| 11 | A | 1回取るごとに玉の個数の差はどうなるかを考えます。 | |
| 12 | D | ヒ | 糸口が分かりにくい問題です。1回目のときは、赤玉が24個残っているので、2回目のときは、1回目よりも箱を8個多く使っていると考えます。2回目のときに、箱を8個減らしたらと考えますが、なかなかの難問です。 |
| 13 | B | テ | 座れる人の差の44人にから、椅子の数の差を求めます。これは面積図で解くメリットはありません。 |
| 14 | C | テ | 差からは考えられないので、和を考えます。「差でダメなときは、和!」と考えることがポイントです。最後はつるかめ算になります。和を考える問題なので、面積図も有効です。 |
| 15 | C | テ | 合計金額の差からAとBの個数の差と、AとCの個数の差を求めます。差の関係が分かったら、Aを求めたいので、Aの個数に揃えます。1番少ないCに揃えても良いです。差集め算の真髄のような問題です。 |
「難」は難度は以下の基準です。
A:確実に解けるようにしたい問題
B:サピックス偏差値50以上を目指す人向けの問題
C:サピックス偏差値60以上を目指す人向けの問題
D:特に難しい問題
※「要」は重要度で以下の基準です(B・C・Dのみ表記)。
ゼ:絶対に解けるようにしたい重要な問題
テ:よく出る典型題
ヒ:捻りのある問題
サ:地道な作業が必要な問題