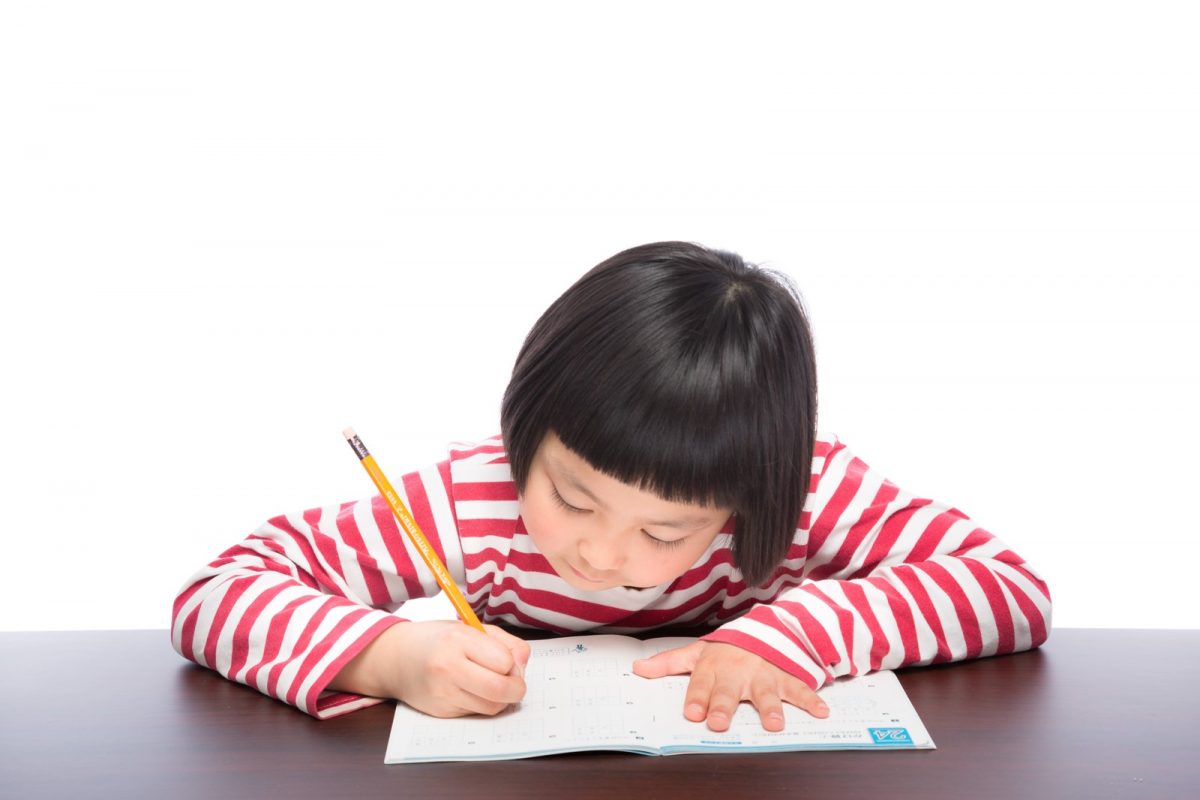- 2019年2月12日
いままでこのブログはコメント欄をつくっていませんでしたが、今回から、コメント欄を開設します。
疑問に思った点、分かりにくい点、などございましたら、お気軽にコメント願います。
また、新たにお知りになりたいことがございましたら、リクエスト願います。
では、本題に入ります。
本屋の学参コーナーに行くと、学習参考書や問題集が勢揃いしています。
通塾していると、基本的に塾から配付されている教材と、指定されている問題集と過去問だけで、十分なはずです。
ところが、通塾している方で、学参コーナーに行かない人はいないと思います。
塾で使っている教材だけでは、いろいろな面で不足しているのでしょう。
かなり優秀で、塾教材だけでは物足りないから、もっとチャレンジしたいという方もいらっしゃいますが、
多くの方が、塾教材は分かりにくいから、もっと分かりやすい教材はないかと探していると思います。
塾教材の役割は、問題演習をすることです。
そのため、問題演習の際にはマル付けも必要なので、解答は必要ですが、
間違えた問題を、しっかり解決することを目指す姿勢は物足りないかもしれません。
分からないところを解決したい消費者と、とにかく量を与えたい生産者のずれが生じています。
ということで、市販の教材が必要になるわけですが、
問題で選び、解説で選ぶことになります。
求めているレベルの問題が揃っていたら購入候補となります。
良問が満載の問題集を選びたいところですが、何が良問かは分かりにくいので、
良問にこだわることはないと思います。
いままで学習してきたレベルの問題を基準に、それより上か、同等か、下かを判断して、
希望に添うものを候補にすれば良いと思います。
問題のレベルでいくつか候補を決めましたら、あとは解説次第です。
解説が良くなければ、購入する意味がまったくないと言っても言い過ぎではありません。
解説が良いというのはどういうものを指すのでしょうか?
私は、読みやすさ、見やすさが最も重要だと思います。
読みやすさとは、文章が多ければプラスポイントではありません。
文章が少なければマイナスポイントです。
算数が得意ではない子は、どうしてそういう計算をしているか分かっていません。
4年生頃は、なんとなく割っていたりかけていたりするだけで正解になるので、
算数が得意だと評価しがちですが、「なんとなく」の学習ではすぐに限界がきます。
問題集を扱うことで、そういった悪い癖も修正できれば理想的です。
そのためには「○○なので、□□する」という記述が多くあった方が良いです。
計算をするときは、必ず理由と目的があります。
目的というのは正解にするためという遠い目標ではなく、
何を求めるための計算をしているか把握していることです。
「○○を求めたいので」に続けて計算式が書いてあると効果的です。
そういった点を考慮されている解説が、読みやすい解説だと思います。
案外少ないです。
当教材の小5集中割合第1回の解説を見てみましたら、
ある問題の解説の冒頭で
分数は使いたくないので、Aは全体の5分の2というところから、全体を5にしたいところですが、
もう少し先読みして5と7の最小公倍数の35にします。
と書いてありました。
これは特にすごいことは書いていませんが、理由と目的を明確にするということはこういうことです。
こういう文章を毎回のようにサラッと載せることで、自然と論理がつながっていくような気がします。
見やすさの判断は簡単です。
読みやすさの判断は解説を目を通して、理由と目的があるかを確認しますが、
見やすさの判断は一瞬でできます。
見やすいか見やすくないかではありません。
レイアウトまで含めて真似ができるかどうかです。
算数の学力とは、定型化された解き方ができるかどうかなので、
基礎学力育成の段階では、定型化していくことが大切です。
そのためには、問題集の解説を見て、「こうやって書こう!」と思わなくては効果がありません。
紙面の都合でギュウギュウに詰まった解説もよく見かけますが、本末転倒なのでは?と思ってしまいます。
当教材の平面図形や立体図形の解説は、よく一部分だけかいています。
(立体図形を、平面に注目して、平面図形として解いていくのは重要な解法ですし)
場合によっては、そのときに使わない線は消してしまいます。
それは、分かりやすさに拘ってという面もありますが、
問題を解く生徒さんに、こういうシンプルな図を自力で描いて解いて欲しいと考えているからです。
立体図形や複雑な平面図形は描くのが大変ですが、部分的に描くだけなら容易です。
平面図形や立体図形以外でもレイアウトが解法力に大きく関わる単元は
- 規則性
- 場合の数
- 速さ
- 食塩水
- 売買損益算
- ニュートン算
- 仕事算
- 過不足算
書いていくとキリがありません。
問題レベルで候補を絞って、読みやすさでさらに絞って、見やすさ(レイアウト)で決定として、
というように選んでいくと、ピッタリな良問題集を手にすることができます。