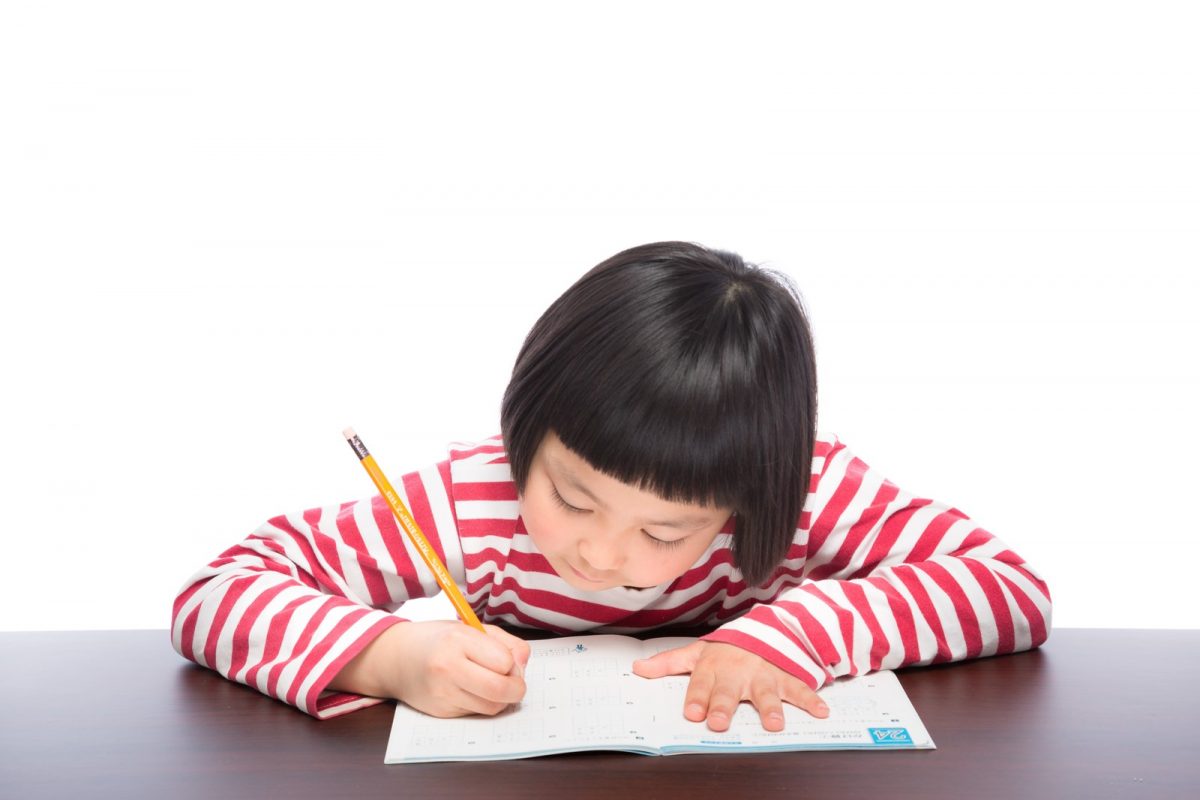受験勉強のタイプを見極める
――頭が良い子と、一般的な子では「正しい勉強法」が違う
受験業界ではあまり言われませんが、特別に頭の良い子と、一般的な子では、受験勉強の進め方はまったく異なります。
そして今の中学受験の主流は――
残念ながら「頭が良い子向け」に作られています。
だから、「ちゃんとやっているのに成果が出ない」「どれだけ頑張っても算数が伸びない」と感じるご家庭が多いのは、ある意味、必然なのです。
「頭が良い子向け」の受験算数とは
いわゆる“特別に頭の良い子”の受験勉強は、非常にシンプルです。
ひたすら問題を解くだけ。
これで十分なのです。
適度な負荷のある問題を次々に解くことで、思考が広がり、発見が増え、理解が深まる。
量をこなすことで質が上がる――この好循環が自然に生まれます。
つまり、「まずやること」が正解になってしまうタイプです。
SNSではよく「質と量、どちらが大事?」という議論を見ますが、頭の良い子の場合は、“量”が質を生むという世界にいます。
一般的な子に「量」は効かない理由
一方、一般的な子の場合は、同じように問題を解いても、「解き方を覚えるだけ」で終わってしまうことが多いのです。
応用力は上がらず、視野も広がらない。
極端に言えば、“解いた問題だけが解けるようになる”という状態です。
この違いは、才能やIQの問題ではありません。
本質的には、「やりながら多方面に気づけるかどうか」、つまり好奇心の強さです。
「頭の良さ」と「好奇心」は別物
ここで言う“頭の良い子”というのは、いわゆる成績優秀という意味ではなく、何かをやりながら、「あれ?これってこういうことかな?」と気づきを広げていける子のことです。
逆に、いくら地頭が良くても、好奇心が薄ければ、受験では“一般的な子”のタイプに入ります。
つまりこれは、優劣の話ではなく、タイプの話です。
一般的な子は「量」より「会話」で伸びる
一般的な子に、頭の良い子と同じ「量をこなす勉強」を課しても、成果は出にくいです。
むしろ、算数の話をたくさん会話することが効果的です。
「どうしてそうするの?」
「それをやると何が分かるの?」
「この考え方、他の問題でも使えそう?」
こうした会話を通して、「算数をどう捉えるか」という根っこの部分が磨かれ、思考の構造が少しずつ作られていきます。
私はいろいろな方法を試してきましたが、最終的に会話に勝るものはないと感じています。
勉強法を決める前に「タイプを確認する」
受験勉強を本格的に始める4年生以降、自分の子どもがどのタイプなのかを見極めずに、「正しい勉強法」に突入するのは危険です。
途中で「やり方を変える」のは、精神的にも大きな負担です。
最初から合ったスタイルで始めることが理想です。
その“見極め”に最適なのが、書き出し練習です。
「書き出し練習」で見える“考える力”
書き出し練習というのは、たとえば――
「9月18日は、日付の数字を足すと9+1+8=18になります。では、たして10になる日を全部書き出しなさい。」
のような問題です。
条件が少なく、作業と発想の両方が必要なタイプの問題。
1問目でコツを少し見せてあげたら、あとは本人が集中して、最後まで自分で書き出せるかどうか。
間違えても投げ出さず、正解になるまで意欲的にチャレンジできるかどうか。
この姿勢こそが、「頭の良さ」や「好奇心の深さ」を映す鏡です。
書き出し練習で見えるタイプ判定
- 集中して取り組み、考えながら楽しめる → 頭の良い子(=好奇心型)
- 作業を嫌がり、早く答えを知りたがる → 一般的な子(=受け身型)
書き出し練習がスムーズに進む子が、4年生以降に伸び悩むことは、私の経験上ほとんどありません。
一方で、この段階で苦戦する子が、あとから“特別に頭の良いタイプ”に化けることも、まずありません。
つまり、書き出し練習は頭の良さを測るテストではなく、「自分の子がどんな学び方で伸びるか」を見極めるテストなのです。
勉強法は“タイプに合わせる”
スポーツの世界でも、球技・陸上・水泳――
同じ運動でも、タイプに合わせて練習方法が全く違います。
受験勉強も同じです。
短距離型の練習を長距離ランナーにさせても、結果は出ません。
大切なのは、タイプに合った学習スタンスを選ぶこと。
- 問題量で思考が広がるタイプ → 量をこなす勉強法でOK
- 会話や構造理解で深めるタイプ → 丁寧に対話を重ねる勉強法が最適
どちらが優れているという話ではなく、「合うスタイルを選ぶかどうか」が、結果を左右します。
まとめ
受験業界ではなかなか語られませんが、「頭が良い子向けの勉強法」は、全員にとっての正解ではありません。
- 問題をどんどん解いて伸びるタイプ
- 対話や構造理解で伸びるタイプ
子どものタイプを見極め、それに合わせた方法を選ぶことが、遠回りのようで最も確実な近道です。
受験は「努力量」よりも、「努力の方向」で結果が決まります。
そしてその方向を見つける第一歩が――
書き出し練習なのです。