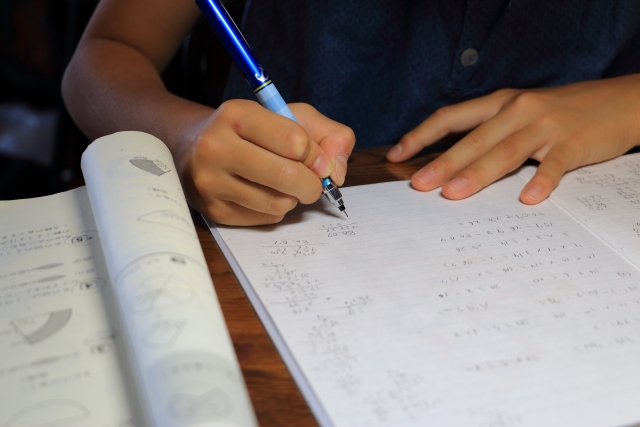- 2023年6月28日
応用力がある子とない子がいます。
もちろん、応用力はあった方が良いです。
難関校を目指すとしたら、十分な応用力が欲しいです。
難関中の入試本番での得点力や、6年生後期の模試の成績は応用力が大きく影響します。
とてもよくできる子だと思っていたけど、最後、伸び悩んでしまう子は、結局は応用力が足りなかったのかなと思うことが多いです。
ミスを気にする方が多いですが(ミスがなければ偏差値○○だったなど)、ミスの有無よりも100倍くらい応用力の有無の方が大切です。
では、応用力はどうしたらつくのでしょうか?
回答は簡単で、勉強をしたら応用力がつきます。
地頭とか資質とかで、どのくらいの勉強でどのくらいの応用力がつくとか、どんなに頑張ってもこんな応用力はつかないというようなものもありますが、勉強をすれば、誰でも目指しているくらいの応用力はつきます。
ところが、応用力とはまるで関係のない勉強をしても、応用力はつきません。
応用力がつくような勉強をするかどうかです。
かなりもったいぶった書き方をしてきましたが、応用力のつく学習方法を書いていきたいと思います。
それは、他の教科にも共通することですが、考える勉強をしているかどうかです。
誤解しやすいですが、問題を解くときに1問を10分くらい考えていたとします。
解けた場合でも、解けなかった場合でも、考えている時間は1分程度かもしれません。
作業や計算は、余程、工夫して進めていかないと、考えている時間にはカウントできません。
問題が解けなかったとしたら、考えている時間は10秒くらいだったということも珍しくないと思います。
スポーツであれば、100m走るとか、100m泳ぐという数値があって分かりやすいですが、勉強の場合、特に、考える時間は目に見えないものなので、考えているかどうかの判断が難しいです。
問題を解いているんだから、考えているはずと決めるのはよくありません。
しっかり考える時間を長く取ることがポイントになります。
解けないときは解説を見ますが、その解説を見る時間も、子供によっては考えながら見る子もいれば、考えずに、理解しよう、覚えようとする子もいます。
「理解する」「覚える」と、「考える」は異なるものだと思っています。
「理解する」ことは大切ですが、応用力にはあまり影響しません。
確実に考えている時間にカウントできるのは、算数では、解くときの書き方を工夫している時間です。
思考力問題ならば、いままでの知識を使って、どういう書き方をすれば、考えやすくなり、解きやすくなるかを考えて書きます。
こういう書き方を初めてやってみました
この言葉が頻繁に出てくるかどうかです。
それが出てくれば、考えて問題を解いていることになり、応用力がつきます。
典型題だと書き方を工夫するのは難しいですが、少しでも効率化して、「これでも解ける!」となっても、「やっぱりこれではダメ…」となってもいいので、オリジナルの書き方をいろいろ試すことができれば、考えていることになります。
いま、典型題の場合も書きましたが、思考力問題や初見の問題の方が書き方を工夫しやすいのは確かです。
つまり、思考力問題を初めての書き方で解くことがポイントになります。
書き方の定まった問題を、定まった通りに解いて正解にしても、それは計算練習をしているに過ぎません。
計算練習がいけないわけではなく、その勉強だけでは、考える時間が取れず、応用力がつかないということになります。
よく男女の性差で男子の方が算数が得意と言われます。
能力の差もあるかもしれませんが、私見では、女子の方が勉強に対して真面目な子が多く、経験した解き方や書き方の枠からなかなか出ない傾向があります。
男子の方が過去にとらわれすぎずに問題に応じてオリジナルの解き方をしている傾向があります。
女子が優秀で、男子がだらしないという見方もできますが、算数の応用力に関しては、考えてオリジナルの書き方で解く習慣のある男子の方が応用力がつきやすいのではないかと思います。
なかなか枠から出られない女子にアドバイスをするとしたら、いままでの知識を元に、自分で考えた新しい書き方で解くことをどこかでやる必要があるよという言葉を与えたいです。
算数の講師に解き方を教わったときは、「同じものを書けば解ける!」と捉えるのではなく、「こんな感じで解いても解けるんだ」「この解法を今度どこかで使ってみよう」という上から見る感覚があると良いです。
算数に限りませんが、学問は謙虚で素直ではダメだと思います。
「先生の言う通りにします」ではなく、自分の意見を持って、「どうしてこれではダメなんですか?」というくらいの強気な姿勢が必要です。
私は指導者として、そのくらい生意気な生徒さん(お客様に対して言葉は悪いですが)の方が、学力向上の可能性を感じ、頼もしく思います。
よく、素直な子の方が伸びるという意見を見ることがあります。
私は、それは「典型題が早く身につくだけ」だと解釈しています。
指導者は教えた直後に解ける子を優秀だと思う傾向があります。
難関校を目指して、応用力を高めたいならば、素直かどうかではなく、オリジナルの書き方を編み出す姿勢があるかが問われます。
現在のスカイプ指導では、正解でも不正解でも、どう考えたか確認することが多いです。
論理がおかしいときは、「それで何が求められたの?」と確認します。
その返答ができなかったり、実際には何も求められていない場合は、考えていないことになります。
適当に計算しただけに過ぎません。
「○○を求めたの?」と思ってしまう意外な返答をする子もいますが、もう少し確認してみると、案外、遠回りでも、その子なりに手順を踏んで考えを進めている場合があります。
そういうときは、正直に「遠回りしているけど、ちゃんと繋がっていて、よく考えて解いているね」と評価します。
その評価が、応用力がつく勉強ができていると認めている言葉になります。
初見の問題を自分なりに考えて、それを伝わる言葉で説明ができれば、オリジナルの書き方で解くことはすぐ近くです。
オリジナルの書き方で解けるように、考え方を説明してもらっていると言っても良いです。
実際に「何でもいいから書いてごらん」というと、なかなか工夫された良いものを書く子が多いです。
年々、私が教えている生徒さんたちは、考えて解いて、考え方を説明できる子が増えています。
生まれつき考える習慣ができていたわけではなくて、厳しいとは思いますが、「考えていない勉強は勉強じゃない」という姿勢を強く打ち出しているからだと思います。
生徒さんに考える習慣ができてしまえば、指導者としてはとても楽で、「まずは何でもいいから何か書こうよ」「算数に関する雑談」「ときどき模範的な書き方を見せる」だけで、オリジナルの書き方ができるようになり、応用力がついていきます。
応用力は先天的なものとしないで、新しい書き方にチャレンジする姿勢から生まれてくるものと捉えると良いと思います。