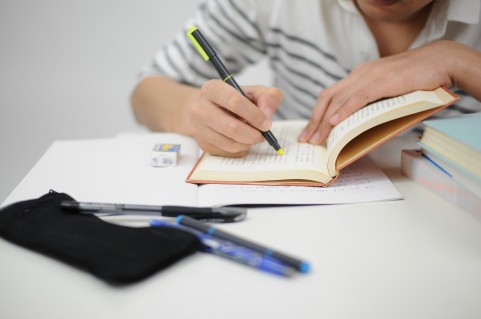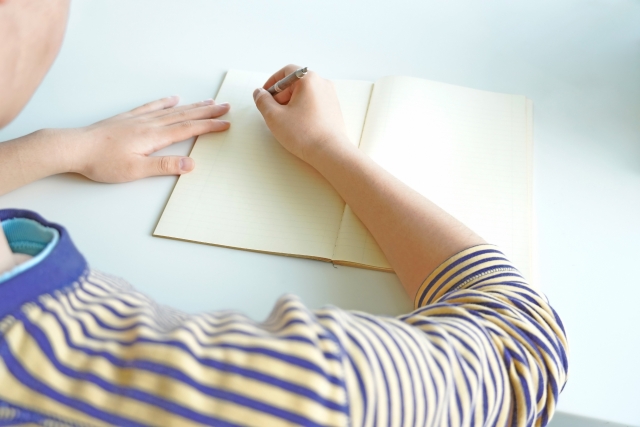保護者は算数を教えた方が良いのか?
――教えるより「支える」が上手くいく
子どもが算数で苦戦しているとき、保護者が「一緒に勉強してあげたい」「なんとか理解させてあげたい」と思うのは自然なことです。
でも、「教え方を知らないから、教えたらかえってマイナスにならないか」「どこまで教えたらいいのか」と悩む方も多いでしょう。
今回は、親が子に算数を教えるときに大切な考え方をお伝えします。
「教える」目的を勘違いしない
家庭教師の仕事は「教えること」ですが、実際の目的は「生徒が自分で解けるようにすること」です。
その観点から言えば、教えすぎるのは逆効果です。
むしろ、「少し我慢して待つ」方が成果につながるケースが多いのです。
SNSなどでは「教えないことが大切」といった極端な意見も見かけます。
それを鵜呑みにする必要はありませんが、“教えすぎはよくない”という点だけは真実です。
保護者におすすめの関わり方
教えるのではなく、「考えるきっかけを与える」ことがポイントです。
具体的には、次のような質問をしてみてください。
- 「この式で何を求めたの?」
- 「どうしてこの図を描いたの?」
- 「条件はすべて図に書いた?」
こうした問いかけをして、子どもの答えをじっくり待ちましょう。
分からないようなら少し戻って、「この図はどういう意味かな?」とやさしく掘り下げていけばOKです。
すぐに教えない。考える時間を奪わない。
それだけで、子どもは少しずつ自分の思考を整理できるようになります。
釣りと同じ、“やらせて考えさせる”のが上達のコツ
ちょっと釣りの話をしてみましょう。
親子で釣りに行ったとして――
もし親が、子どもの釣り竿まで取り上げて魚を釣り始めたらどうなるでしょうか?
きっと子どもはポカンと見て終わりです。
「この場所が良いよ」
「エサはこうやって付けるんだよ」
それくらいのアドバイスで十分です。
あとは本人が竿を握り、糸を垂らしてみる。
そして、魚が釣れたあとに糸を切ってしまったり、逃がしてしまったら、そこで、またアドバイスします。
釣れる前から、講釈を垂れる必要はありません。
実は、この釣りのイメージこそ、算数のフォローととても近いのです。
親の役割は「魚を釣る人」ではなく、「釣れる環境を整える人」。
支えすぎず、放り出しすぎず、釣りの(算数の問題を解く)楽しさを体験させる。
その関わり方こそが、子どもの「考える力」を最も確実に伸ばします。
支えることが「教える」よりも力になる
親が隣にいてくれるだけで、子どもは安心して問題に向かうことができます。
自転車の練習で、後ろを親が支えてくれていると思い込んでスイスイこいでいた子が、ふと後ろを見た瞬間に転んでしまう――そんな場面を見たことはありませんか?
算数の学習もそれに似ています。
まだバランスが取れないうちは、「支えられている」と感じながら考える方が上達が早いのです。
解法力が十分に身についた子なら「もう支えはいらない」と言うでしょう。
でもそうでないうちは、支えがあることで思考のエネルギーを前向きに使えるのです。
解説の“使い方”にも落とし穴がある
「解説があれば親でも教えられる」と思われる方も多いですが、実はここにも落とし穴があります。
解説をそのまま読み聞かせても、子どもは“分かったつもり”で終わることが多いのです。
大切なのは、解説を“読む”のではなく、“使う”こと。
多くの保護者は、解説を「解き進めるための押し出す力」として使いがちです。
でも、本当に力をつけたいなら、解説を“抵抗”に変えることが大切です。
つまり、解説を使ってスムーズに進ませるのではなく、あえて立ち止まり、「なぜこうなるの?」と考えさせるための壁として使うのです。
たとえば、解説の一部を見せて「この式の意味、分かる?」と問いかけたり、すぐに答えを示さず、「じゃあこの次にやることは何だろう?」と考えさせる。
解説を“押し出す力”にしてしまうと、子どもは受け身になります。
でも“抵抗”として立ちはだかると、子どもはそれを乗り越えようと頭を使います。
この“抵抗”こそ、思考力が育つ時間です。
「書く場所」を整えるだけで学びが変わる
保護者におすすめしたいもう一つのサポートが、ノートの作り方を整えることです。
A4ノートに縦線を引き、左右でエリアを分けましょう。
- 左:結果・図・表を書く「まとめエリア」
- 右:筆算や暗算の確認を書く「計算エリア」
バランスは6:4か5:5が目安です。
筆算を小さく隅に書く子が多いですが、それでは間違いが増えます。
「計算をきちんと書くスペースがある」ことが、思考の整理に直結します。
式には2種類ある
算数の式には、実は2種類あります。
- 条件を整理・構造を見える化するための式(考えるための式)
- ただ計算をするための式(作業の式)
前者は必要不可欠ですが、後者は実は不要です。
計算は筆算や暗算で十分です。
つまり――
考えるための式は「結果エリア」に、計算の作業は「筆算エリア」に。
この区別をはっきりさせると、解法の質が向上します。
図や表、線分図、面積図なども「結果エリア」に書きます。
図形問題の場合は、計算結果を図に直接書くのが原則です。
まとめ:親の役割は「教える人」ではなく「支える人」
算数を教えるうえで大切なのは、
- 子どもの思考の時間を奪わない
- 必要なときにヒントを与える
- 解説を敢えて抵抗として“使う”
- ノートを整理して「考える場」を整える
この4点です。
親が「教える人」にならなくても大丈夫です。
子どもが安心して考えられる環境を整えるだけで、算数の力は確実に伸びていきます。