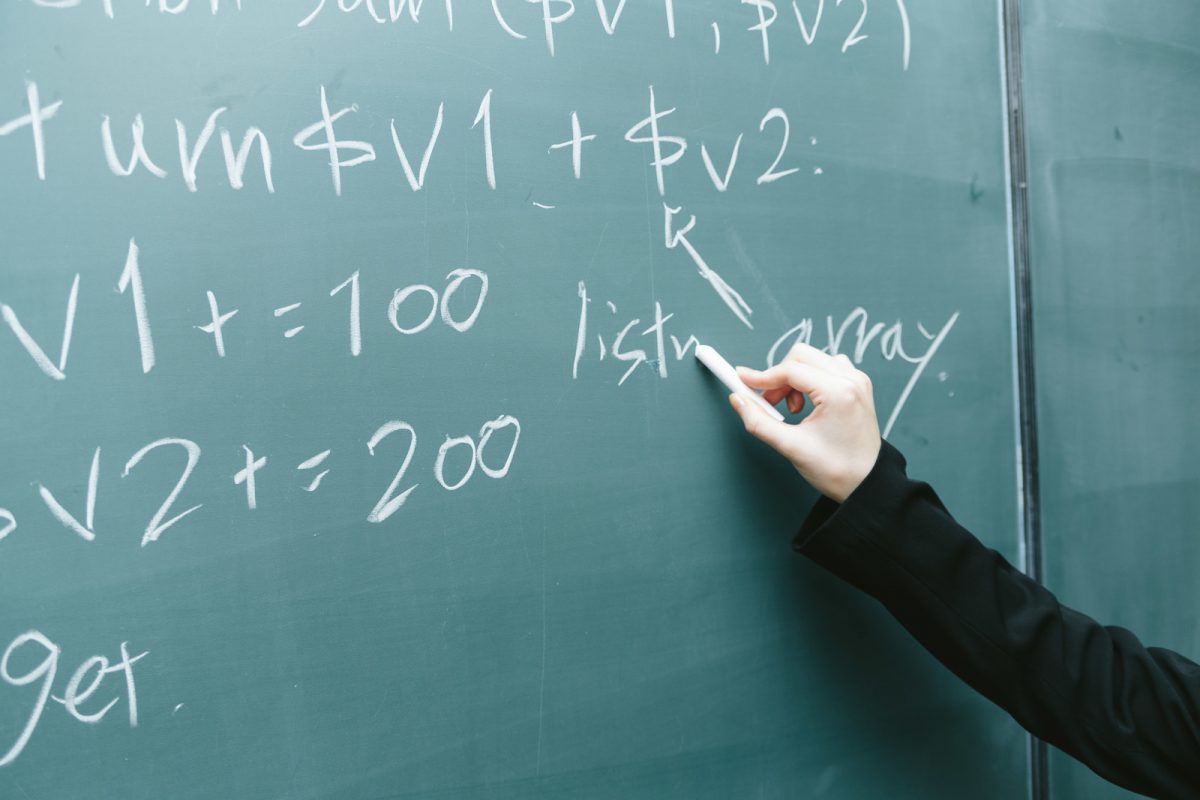受験算数で成功するための素養と心構え
① 先生の話をよく聞く ――分からないままにしない
授業中の先生の一言は、単なる解法説明にとどまりません。
「ここを工夫すると解きやすい」「この考え方は大事だ」――その場でしか聞けないアドバイスが詰まっています。
ただし、子どもなので先生の言葉の意味が分からないこともあります。
そこで大切なのは、聞き直そうとする姿勢を育てることです。
本来なら「分からないときに聞き流す」というのは、気持ち悪くて居心地の悪い行動のはずです。
しかし、分からないことをそのままにする習慣をつけてしまうと、――不思議なことに、その“違和感”がだんだん麻痺していきます。
最初は「え、分からなかった…どうしよう」とソワソワしていたのに、やがて「まあ、分からなくてもいいや」に変わり、最後には「先生の話を真剣に聞かないのが普通」になってしまいます。
こうして、授業の大事な部分を聞き取る力そのものが落ちていくのです。
これは本当に怖いことです。
逆に、「分からないことをすぐに質問して解決する」習慣を持っている子は、先生の言葉を一つ残らず“栄養”にできます。
② 計算は速く、正確に、そして必ず検算
算数の基礎は計算力です。
速さと正確さを両立させることが重要です。
基本は暗算ですが、暗算は間違いやすいもの。
だからこそ、求めた直後に「大丈夫かな?」と確認する習慣を持つことが大切です。
慎重に見直し、必要ならすぐに検算。
ここでよくあるのが――
「暗算で間違えたから、暗算はダメ!」という結論。
いやいや、それは大間違いです。
暗算の最大の武器はスピード。
そして弱点は「うっかり間違える」こと。
つまり、検算をすれば弱点は消えて、利点だけが残るのです(暗算なら、検算をしても、すっきり速いからです)。
暗算を敵視するのは、車を運転して事故ったから「車なんて全部危ない!」と言っているのと同じ。
交通ルール(=検算)を守れば、安全で速い最高の乗り物なのです。
→ 暗算+検算=最強。間違えても暗算単体を悪者にしないでください。
③ 慌てない ――「疑う」習慣を持つ
子どもは「分かった!できた!」と思った瞬間に、もう脳内では勝利宣言を上げてしまいます。
そこから先の確認を怠ることで、浅い思考のクセがどんどん強化されてしまうのです。
「自分は正しい」と思ったまま突っ走る習慣がつくと、問題を深く考える力が育ちません。
その場しのぎの“速答型”になってしまい、難問に太刀打ちできなくなるのです。
だからこそ大事なのは――
「落ち着いて、本当にこれでいいかな?」と自分に問い直すこと。
この“疑う一瞬”が、ただの浅い思考を防ぎ、受験算数に必須の“深い思考”へと導いてくれます。
④ 瞬発力を大切にする ――切り替わった瞬間に全開
受験勉強では「やる気が出てからやる」では遅すぎます。
大事なのは切り替えの瞬間。
- 説明が始まった瞬間に、全神経を集中させて聞く
- 演習が始まった瞬間に、全力で問題に取りかかる
このレスポンスの速さが、成績の差を大きく分けます。
ところが多くの子は、授業が始まってもまだ“助走モード”
説明を聞きながら頭がよそ見していたり、問題を見ても「さて、どこから手をつけようかな」とまだボーッとしていたりします。
受験では、「切り替えた瞬間に全開」のエネルギーが不可欠です。
スイッチを押した瞬間に100%で動ける子ほど、本番でも力を出し切れます。
⑤ 分からなくても手を動かす
「分からない」と止まってしまうのが一番の危険です。
解き方が思いつかなくても、書き出し・図・表などを作って手を動かすこと。
ただし、計算式をでたらめに書くのはNGです。
誤った式を並べても何の意味もありません。
「考えるための作業」をする――この姿勢が大切です。
⑥ 悩みは一人で抱え込まない ――苦手意識を決定づけない
「できない」「分からない」をそのまま放置すると、ただの一問のミスが「自分はこの単元が苦手なんだ」という決定事項になってしまいます。
実際はただの一時的なつまずきでも、動かないでいると“苦手”が固定され、どんどん大きな壁に育っていくのです。
逆に、すぐに先生や父や母や、あるいは友達に相談するだけで、流れは変わります。
意識を“苦手”から少し離すだけで、気持ちが軽くなり、取り組む姿勢も変わるのです。
受験算数においては、この「気持ちの持ち方」こそが、思っている以上に大きな差を生みます。
⑦ 作業に入る前に一度立ち止まる
最後にもうひとつ。
問題を見て「よし、こう解こう」と思ったら、すぐに手を動かすのではなく、一呼吸おいて冷静に考える習慣を身につけましょう。
「この作戦でいいかな?」
「他にもっとシンプルな方法はないかな?」
この立ち止まりがあるだけで、無駄な作業や補助線の乱用を防ぎ、解答の精度が大きく上がります。
まとめ
中学受験の算数は、知識やテクニックの勝負ではありません。
- 分からないままにしない姿勢
- 慎重な確認と冷静な疑い
- 瞬発力と切り替えの速さ
- 手を動かしながら考える粘り強さ
- 相談する勇気
- 作業に入る前の落ち着き
これらの心構えこそ、受験生に必要な「基礎体力」です。
一つひとつの習慣を積み重ねることで、算数の力は確実に伸びていきます。