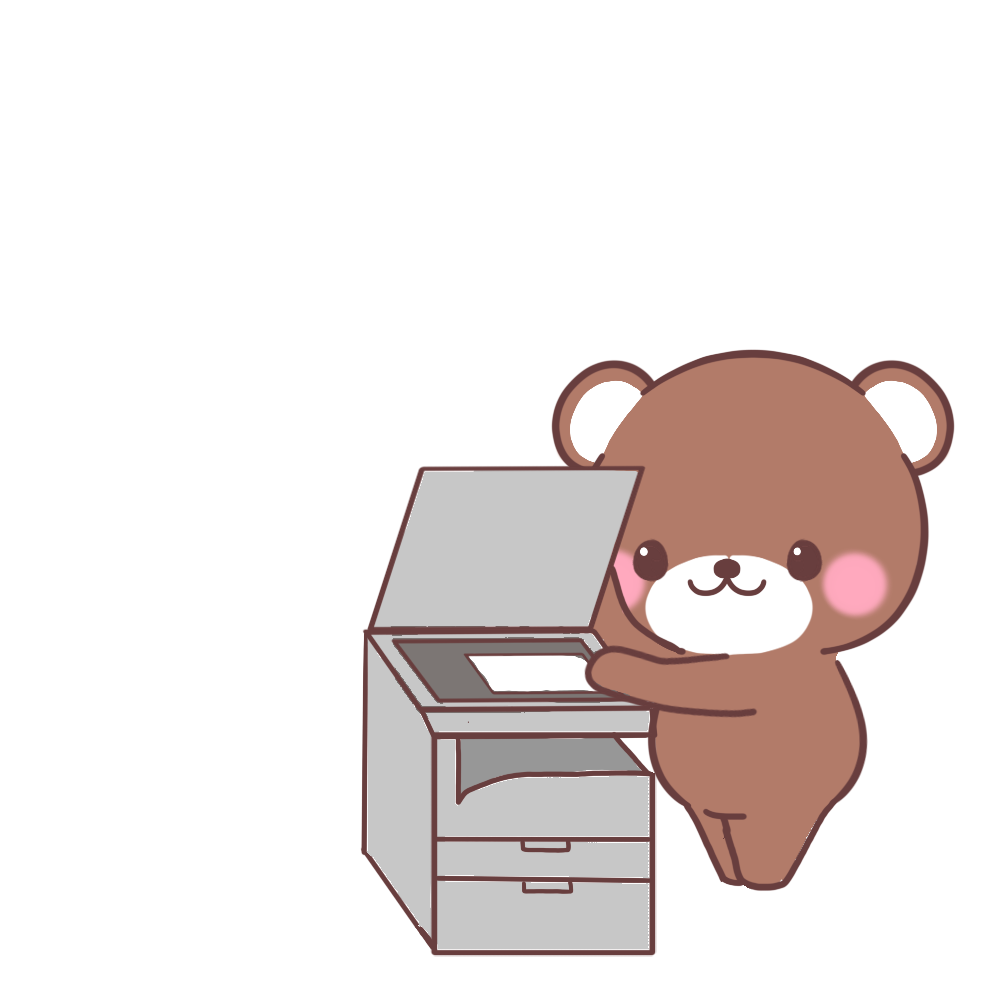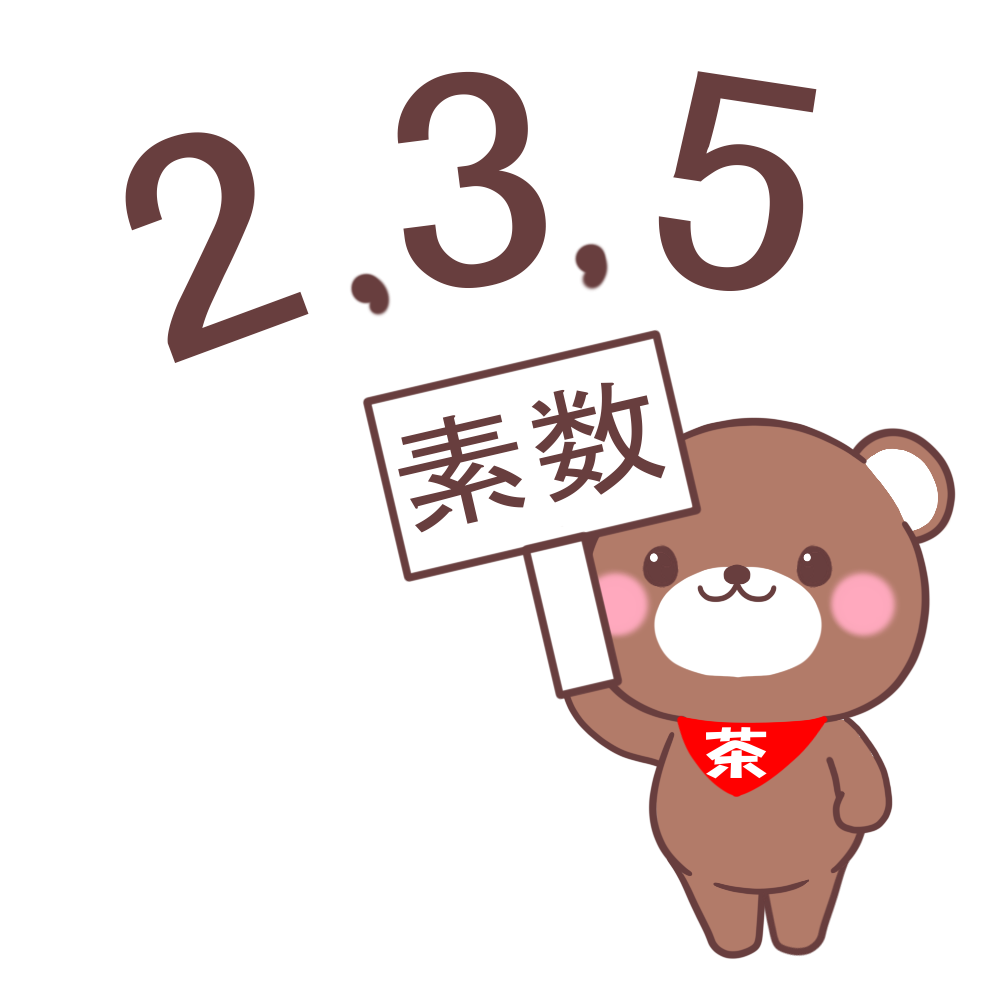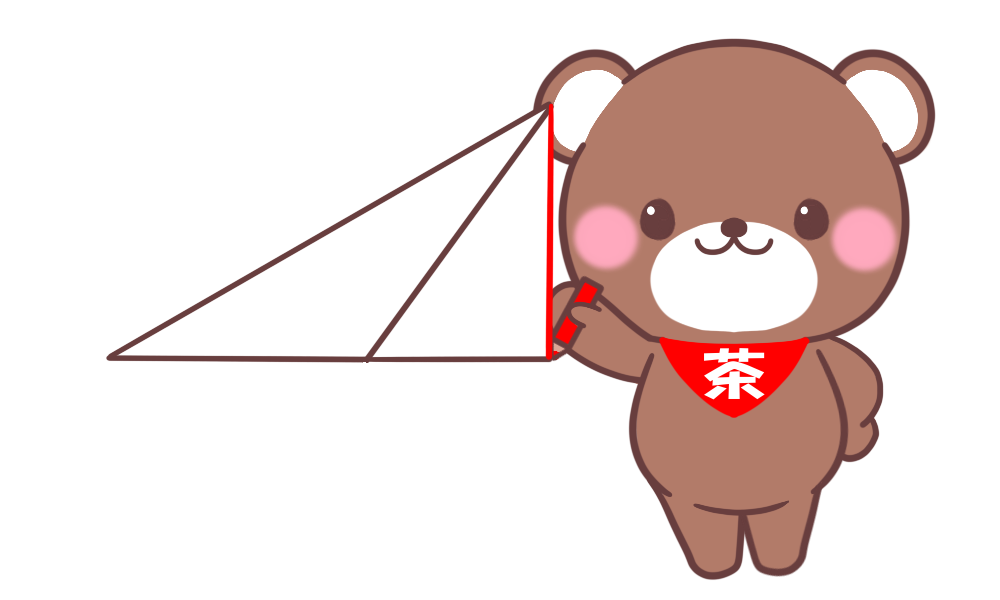- 2023年2月7日
平面図形と比の3回目です。
相似の1回目です。
相似の条件は3つありますが、中学入試に出てくるのは2つの角が等しいのみです。
相似には、ピラミッド型と呼ばれるタイプ(ここではA型と呼んでいます)と、クロス型や砂時計型と呼ばれるタイプ(ここではX型と呼んでいます)と、直角三角形型があります。
A型が最も厄介です。
重なっているので間違いやすいです。
A型がしっかりマスターできてから、X型に進みます。
X型の問題の方が難しいですが、X型は単純なので、対応しやすいと思います。
A型でもX型でも使えるときは、X型を使うことを推奨しています。
興味のある方はこちらにどうぞ
第75話:相似①の概要
75・1
A型の相似です。
2つの三角形が重なっているので間違いやすいです。
すぐに辺の比を求めずに、相似比を確認してから進めることがポイントです。
75・2
A型の相似の図形の面積比の問題です。
2乗する!と覚えるのでは無く、底辺の比、高さの比というように公式をイメージして面積を求める感覚で解くと良いと思います。
75・1もそうですが、それ以上に相似比を意識することがポイントです。
台形に補助線をひいて、三角形と平行四辺形に分ける問題は、隙あらば公式通りに求めるという姿勢が必要です。
75・3
X型の相似です。
三角形の向きが異なりますが、重なっていないのでA型よりも単純です。
面積を求めるときは、相似比を使って、高さを求めます。
75・4
X型の相似の実戦的な問題です。
X型の三角形の相似比を使って図形全体の高さを決めるというのは、平面図形と比の解法の基本骨格です。
75・5
A型とX型の相似が両方入っている問題です。
相似比が分かる方から考えていきます。
相似比が分かったら、他の相似の相似比を求められるように、図に比を書き入れます。
意味の無いところに比を書き入れる人が多いですが、必要なところに比を書き入れられるように練習しましょう。
練習問題
| 番号 | 難 | 要 | 講評 |
| 1 | A | A型の相似です。相似比を考えましょう。 | |
| 2 | A | 8:8:4を小さくしてから、相似比を考えましょう。 | |
| 3 | B | テ | 向きの異なるA型の相似を使い、FGとGFを求めて、公式通りに求めます。 |
| 4 | A | 相似比を面積比に変えます。相似比を考えるようにしましょう。 | |
| 5 | A | 9か所の面積比を書き入れましょう。 | |
| 6 | B | ゼ | A型の三角形と、長方形に分けます。A型の相似を利用して内部の線が分かったら、公式通りに求められます。 |
| 7 | A | X型の相似を利用して、高さの比を求めて、実際の高さを求めます。 | |
| 8 | A | 横に倒れていますが、X型の相似です。相似比を使って、斜線の三角形の高さを求めます。 | |
| 9 | B | ゼ | X型の相似を利用して、全体の半分の直角三角形から、三角形をひきます。 |
| 10 | B | ゼ | 底辺を決めてX型の相似の相似比を求めます。それを利用して、全体の高さを決めます。 |
| 11 | B | ゼ | めもりの数で相似比を求めてしまう人が多発する問題です。底辺の長さを決めることから始めます。相似比を利用して、全体の高さを決めます。 |
| 12 | C | テ | 底辺の長さを決め、X型の相似の相似比を利用して、全体の高さを決め、必要な部分の面積を求めましょう。 |
| 13 | B | ゼ | A型とX型の相似を順に使っていく問題です。相似比が分かる方から取りかかります。 |
| 14 | C | テ | 13番とは図の構造は異なりますが、これもA型とX型の相似を順に使っていきます。X型の相似の相似比を利用して三角形ABCの高さを決めますが、その難度が高めです。 |
| 15 | C | テ | X型の相似から、AE:EBを求めます。EP=PFになることも身につけましょう。 |
「難」は難度は以下の基準です。
A:確実に解けるようにしたい問題
B:サピックス偏差値50以上を目指す人向けの問題
C:サピックス偏差値60以上を目指す人向けの問題
D:特に難しい問題
※「要」は重要度で以下の基準です(B・C・Dのみ表記)。
ゼ:絶対に解けるようにしたい重要な問題
テ:よく出る典型題
ヒ:捻りのある問題
サ:地道な作業が必要な問題